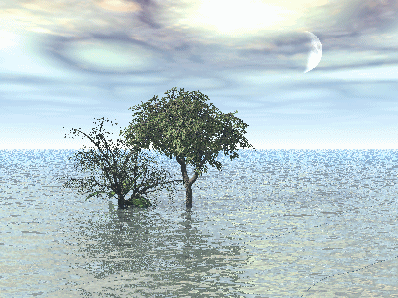
十月初旬。空は快晴。こんな日に、外に出ずに教室にこもって日本文学の授業を受けるなん
て、なんてもったいない風習を人間は考案したんだろう。
て、なんてもったいない風習を人間は考案したんだろう。
窓の外を見ると、詩も評論も何もかも放り出して、秋を満喫しに外へ飛び出したくなる。
けれどわたしは早めに講義棟に入り、窓際の席を陣取った。
秋の空の突き抜けるような高さと、冷たくも暑くもない澄んだ空気。
美しく剪定された樹々に彩られた校庭を朗らかにさざめき歩く学生たち。
赤い瓦屋根とクリーム色の壁の「スパニッシュ・ミッション・スタイル」の建物。
そういった秋の大学の風景の数々を、無味乾燥な授業の合間に教室の窓から楽しみたいが
ために。
ために。
先日、級友に借りた本の題名に何とかのギムナジウム、というのがあったけれども、秋の関
学はそんな言葉にぴったりだと思う。
学はそんな言葉にぴったりだと思う。
ギムナジウムって何だっけ。サナトリウムとどう違うんだっけ。
わたしが長年いたのがサナトリウム、そして今いるのがギムナジウム、これは厳密な定義で
はないけれどまぁそんな感じだ。
はないけれどまぁそんな感じだ。
前の席の川上奈々子が教授にあてられて、中原中也の詩を朗読している。
「在りし日のうた」の中の、「月夜の浜辺」という有名な詩だ。
月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際に、落ちてゐた。
それを拾つて、役立てようと
僕は思つたわけでもないが
なぜだかそれを捨てるに忍びず
僕はそれを、袂(たもと)に入れた。
月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際に、落ちてゐた。
それを拾つて、役立てようと
僕は思つたわけでもないが
月に向つてそれは抛(はふ)れず
浪に向つてそれは抛れず
僕はそれを、袂に入れた。
月夜の晩に、拾つたボタンは
指先に沁(し)み、心に沁みた。
月夜の晩に、拾つたボタンは
どうしてそれが、捨てられようか?
中也は秋の爽涼とした月と星の冴えわたる夜に浜辺を散歩していたのだろうか。
中也が拾ったというボタンは、濡れてキラキラと輝いて見えたのだろうか。
わたしはこの詩が好きだ。特に最後の二行に共感を覚える。わたしも、美しく輝くものは、ど
んなに役にたたないものであっても、捨てることが出来ないから。
んなに役にたたないものであっても、捨てることが出来ないから。
その性格は昔のわたしも今のわたしも変わっていないようで、今のわたしの「家」の「わたし
の部屋」の中には、そういう小さなキラキラしたものがたくさんある。
の部屋」の中には、そういう小さなキラキラしたものがたくさんある。
十年前のわたしはカラスのようにキラキラ煌くものを集めまくっていたらしい。
七色に光るビー玉、色とりどりのおはじき、石屋や宝石屋で袋詰めにして売っている、つるつ
るに磨かれた緑やオレンジや黄色の小石、拾ったらしい貝殻や小石、小さなガラスの細工も
の、そんなものが驚くほどたくさん、さまざまな硝子の壜に入れられて部屋を彩っていた。
るに磨かれた緑やオレンジや黄色の小石、拾ったらしい貝殻や小石、小さなガラスの細工も
の、そんなものが驚くほどたくさん、さまざまな硝子の壜に入れられて部屋を彩っていた。
そして本物だか偽者だか分からないけれど、宝石もたくさん。鑑定士に見てもらわないと値打
ちは不明だが、ダイヤにルビー、アメジストにアクアマリン、トルコ石にサファイア、真珠、珊
瑚、トパーズ……さまざまな種類の宝石がついたピアス、ネックレス、指輪やブレスレット、アン
クレットなどの装身具たちがわたしの鏡台のいちばん上の引き出しに詰まっている。
ちは不明だが、ダイヤにルビー、アメジストにアクアマリン、トルコ石にサファイア、真珠、珊
瑚、トパーズ……さまざまな種類の宝石がついたピアス、ネックレス、指輪やブレスレット、アン
クレットなどの装身具たちがわたしの鏡台のいちばん上の引き出しに詰まっている。
それはすべて、十年以上前に購入したか男にもらったかしたものなので、中には錆びついて
輝きを失っている宝石もあった。
輝きを失っている宝石もあった。
けれど大抵はシルバーではなく十八金かプラチナの台だったので、宝石屋で磨いてもらった
ら綺麗になった。
ら綺麗になった。
その輝きが蘇ったときの何ともいえない感動といったら!
「沙希、沙希……! 当てられてるってば」
後ろの席の高宮陸につつかれて、わたしは反射的に立ち上がり、頬から耳にかけて紅潮す
るのを覚えた。
るのを覚えた。
クラス中の視線がわたしに集まっている。
わたしは記憶にある限り、こんなにたくさんの視線に晒されたことは滅多にないので、人の視
線を意識すると頬が紅く染まってしまうのだ。
線を意識すると頬が紅く染まってしまうのだ。
「……すみません、聞いていませんでした」
斉藤典子教授は、優しいとまではいかないが、寛大な表情を浮かべてうなずいた。わたし
は、というよりもわたしたち輪廻信教出身者たちは、この学校で特別扱いされているのだ。
は、というよりもわたしたち輪廻信教出身者たちは、この学校で特別扱いされているのだ。
「秋空が乙女の感傷を誘っていたのかしら?」
乙女の感傷。乙女、と言われたのは皮肉だろうか。わたしは二十八、もうすぐ二十九になる
のだが。
のだが。
「質問を繰り返しますね。中也のこの詩を書いたときの心境について、あなたはどう想像する
か、ということです」
か、ということです」
「わたしは……」
それはちょうど今、考えていたことだった。
中也はきっと、きらきらしたものが好きだったのだ。と単純にわたしは思うのだけれど、それ
をそのまま答えてしまっては、たぶん斉藤教授の意思にはそぐわないのではないかと思う。
をそのまま答えてしまっては、たぶん斉藤教授の意思にはそぐわないのではないかと思う。
なけなしの知恵を絞って考えた。
「中也は美しいものが好きだったのだと思います。それが、社会的には価値のないものであ
っても。たとえば評価されない詩のように……月夜のボタンはたぶん、中也にとってはかけが
えのない美しい輝きを放っていて、その価値のない美しさを、中也自身の創作に重ね合わせて
いたのだと思うんですが……」
っても。たとえば評価されない詩のように……月夜のボタンはたぶん、中也にとってはかけが
えのない美しい輝きを放っていて、その価値のない美しさを、中也自身の創作に重ね合わせて
いたのだと思うんですが……」
「よろしい。お座りなさい」
月夜の浜辺に落ちていたボタン。
そのかけがえのなさ。それは、わたし自身の姿には重なるものではない。残念なことに。
わたしはたぶん、社会的価値はある。それは特殊な犯罪における被害者としての社会的価
値、だ。
値、だ。
けれども、わたし自身の価値は。
女ざかりを過ぎてしまったこの肉体は、さして美しくないのだ。
いや、心の奥底をたどっていけば、わたしはまだ美しい、美しい、と囁きかける声が聞こえ
る。けれどわたしは大抵その声に耳をふさぐ。自惚れは醜態のもとだから。
る。けれどわたしは大抵その声に耳をふさぐ。自惚れは醜態のもとだから。
わたしの精神だけは、まだ本当に価値を失っていないと確信していたい。どうか。
チャイムが鳴った。鐘の音は古式ゆかしく、秋の蒼空に鳴り響く。
昼休みだ。
学内がさざめくのが皮膚に伝わってくる。この学校の生徒たちは、晴れた秋空にも負けない
ほど年がら年中陽気で、黙することを知らないかのようだ。
ほど年がら年中陽気で、黙することを知らないかのようだ。
「学食、行く?」
後ろの席に座っていた高宮陸が話しかけてくる。陸は19歳、大学一年。
173センチほどの中背、痩せ型。
そばかすのある色白の肌はわたしと似ていて、ときどき姉弟みたいやね、と人にからかわれ
る。
る。
でも顔はそんなに似ていない。陸の瞼は奥二重で、眼は切れ長。鼻は丸くて低い。口は大き
い。何だかミッキーマウスに似ている。ちょっとファニーフェイスだけれど、長めの髪はさらさら
で、とてもハンサムだと思う。
い。何だかミッキーマウスに似ている。ちょっとファニーフェイスだけれど、長めの髪はさらさら
で、とてもハンサムだと思う。
陸はわたしの古くからのボーイフレンドだ。残念ながら、恋人という訳ではないけれど。でも、
わたしは陸に恋をしているのかもしれない。
わたしは陸に恋をしているのかもしれない。
「わたし、お弁当持ってきてん。陸はお弁当なし? パンか何か買って、中庭で食べない?
この陽気だし、学食で食べるのもったいないよ」
この陽気だし、学食で食べるのもったいないよ」
「お弁当かぁ。自分で作ってるの? いつもマメやなぁ。そうやな、じゃあ何か買って外で食べ
ようか」
ようか」
関西学院大学。この学校は、美しいばかりではなく、食の環境も充実していて、ステーキの三
田屋があったりするのには驚いてしまう。
田屋があったりするのには驚いてしまう。
学食のメニューも美味しい。パンも、学校の内外で買うことができて、なかなか美味しいもの
が多いのだ。
が多いのだ。
陸は半熟卵とエビカツの入ったサンドイッチとハムの入ったフレンチトースト、栗アンパンを学
食の購買部で買った。わたし達は中庭に陣取った。空気が美味しい。気持ちいい。気候もいい
し、陸が傍にいるこんな昼休みは、ご飯がいつもより美味しく食べられてしまう。その陸は勢い
よくパンにかぶりついている。
食の購買部で買った。わたし達は中庭に陣取った。空気が美味しい。気持ちいい。気候もいい
し、陸が傍にいるこんな昼休みは、ご飯がいつもより美味しく食べられてしまう。その陸は勢い
よくパンにかぶりついている。
中央芝生の最奥にそびえ立つ時計台の後ろに、甲山がこんもりとまるく鮮やかな緑の雄姿を
見せている。
見せている。
赤い屋根の時計台の左右には、これも赤い屋根の校舎。
関西学院大学は、兵庫県西宮市上ヶ原に建つ、私立のキリスト教系の大学だ。設立は明治
二十二年。伝統のある大学だ。
二十二年。伝統のある大学だ。
わたしは他の大学にあまり遊びに行った記憶もないけれど、日本に、ここ以上に美しいキャ
ンパスがあるだろうか。
ンパスがあるだろうか。
正門から構内に入れば、右手にはランバス記念礼拝堂。休みの日には、ここでよく卒業生が
結婚式を挙げている。
結婚式を挙げている。
ちょっとしたパターゴルフが出来そうな手入れの行き届いた中庭の緑の芝生を、ぐるりと赤い
屋根の背の低い校舎が囲む。
屋根の背の低い校舎が囲む。
広々とした空間の中に、いかにも学生らしいおしゃべりの声、そして部活の運動部の鋭いか
け声、楽器の音、合唱の声……。青春だなぁ、大学だなぁ、とわたしは毎日馬鹿のように感動
をおぼえる。ああ、生きていてよかった、と思う。わたしの育った境遇を知らない人から見れば
大袈裟な感慨かもしれないけれど。
け声、楽器の音、合唱の声……。青春だなぁ、大学だなぁ、とわたしは毎日馬鹿のように感動
をおぼえる。ああ、生きていてよかった、と思う。わたしの育った境遇を知らない人から見れば
大袈裟な感慨かもしれないけれど。
でも陸はわたしに共感してくれる。それだけでいい。わたしは陸と共鳴できればそれで幸せな
のだ。
のだ。
今は10月上旬でまだ紅葉もまばらだけれど、もうひと月もたてば構内は美しく赤と金色の
樹々で染め上げられるはずだ。わたしがはじめて経験する愛する関学の秋。
樹々で染め上げられるはずだ。わたしがはじめて経験する愛する関学の秋。
「また葡萄?」
陸がわたしのお弁当箱を覗き込んでいた。わたしはお弁当を食べ終わり、デザートのタッパ
をあけていた。
をあけていた。
「葡萄大好きなんだもん。季節モノだしー」
「今日は何? マスカット? いいなぁ」
わたしは陸に、幾つぶかの葡萄を分けてあげた。マスカットは甘酸っぱくて、何ともいえない
香りが好き。巨峰も甘くておいしいけれど、香りはやっぱりマスカット。
香りが好き。巨峰も甘くておいしいけれど、香りはやっぱりマスカット。
「あー。気持ちいいなぁー」
陸が芝生に寝転ぶ。
「うー。おなかいっぱいー」
わたしも寝転んでみる。青い空が視界いっぱいに広がり、暖かい太陽の光に吸い込まれそ
う。陸と二人で吸い込まれてしまいたい。気持ちいい。緩やかに風が吹いた。どこからか甘い
キンモクセイの香りが微かに漂ってくる。
う。陸と二人で吸い込まれてしまいたい。気持ちいい。緩やかに風が吹いた。どこからか甘い
キンモクセイの香りが微かに漂ってくる。
うっとりとしていたら、陸が起き上がりこぼしのようにごろりと起き上がったので、わたしは少し
驚いた。
驚いた。
「げ! ぼく、フラ語予習してへんわ! 沙希、やってきた?」
「あー、やってへんわ。ごめん。わたし、今日の午後はフラ語やなくて、月に一度のカウンセリ
ング・ターイム! やの」
ング・ターイム! やの」
「あ、そっか。そうやったな。……あれ? 修一さんとお母さん、校門のところにいてはるや
ん」
ん」
「……」
十五分ほど前から二人はそこにいた。修一の百九十センチ近い長身は、どこにいても目立
つ。わたしは知っていて、知らんぷりをしていたのだ。
つ。わたしは知っていて、知らんぷりをしていたのだ。
「あ、岡野! フラ語予習やってる?」
陸は通りかかったクラスメイトに聞いた。
「何や、またやってへんのか」
「忘れとった。なぁ、頼むわ」
「何かくれる?」
「今度カラオケおごったる」
「よっしゃ。フリータイムでいこかー」
「ち。……沙希、んじゃ、ぼく、教室行くわ。今日あたり、当たるねん」
「了解。岡野くん、ごめんね、こんなボケで。あまり甘やかさんとってよ」
「沙希ちゃん、陸はまかしとき。びしばし鍛えたるでぇ」
「何やねん」
陸は岡野君とともに、一陣の風のように去ってしまった。陸の行動は何につけても早くて、風
といえば格好いいけど、漫才の終わりの唐突さに似ている、とわたしはときどき思う。
といえば格好いいけど、漫才の終わりの唐突さに似ている、とわたしはときどき思う。
そして、ため息をついてのろのろと弁当箱を鞄に片付ける。下を向いている間に、二つの影
がこちらへ伸びてくるのが目に入った。陸が去るのを待ちかねたように、母と、修一が近づい
てきたのだ。
がこちらへ伸びてくるのが目に入った。陸が去るのを待ちかねたように、母と、修一が近づい
てきたのだ。
「沙希。またあんな子と一緒に食事なんてして」
「……ずいぶん、早く来たんやね」
「時間に遅れたら、先生に申し訳ないもの。それにしても沙希、高宮くんが何者か本当にあん
たは分かってるの? あんたをこんな目に合わせた張本人の息子じゃないの!」
たは分かってるの? あんたをこんな目に合わせた張本人の息子じゃないの!」
「お母さん、声が大きいよ。やめてよ。陸は何も悪いことなんてしてないわよ。この十年、どれ
だけ彼が優しかったか。お母さんには分からへんわよ。彼だって被害者やのよ」
だけ彼が優しかったか。お母さんには分からへんわよ。彼だって被害者やのよ」
「……それは、理屈ではそうかもしれないけれど。だけど血筋ってものがあるじゃない。悪者
の子供は悪い血をひくのよ」
の子供は悪い血をひくのよ」
「何てことを言うのよ! 陸はわたしの親友なのに」
「まあいいわ。それより急ぎましょう。鐘が鳴ってるわ。沢崎先生がお待ちやわ」
「あんな奴、わたし達が行かなかったら、仕事がひとつ減ってラッキーって思うだけよ」
「沙希!」
「お母さんだって分かってるでしょう。あの人は仕事で、義務的に派遣されて、それをのろの
ろと形だけこなしてるだけやん」
ろと形だけこなしてるだけやん」
黙っていた修一が、口を開いた。
「沙希、それでも、沢崎先生はプロの医者や。薬ももらわんとあかんやろ? 行こう」
わたしだって分かっている。駄々をこねるなんて不合理だしみっともないし甘えてるって。
それでも、わたしはどうしても沢崎を好きになれない。あのオジサンにわたし達の苦しみの何
が分かるというのだろう。
が分かるというのだろう。
わたしは学校が好きだし、友達も好きだし、そんなに苦しんでいる訳でもない。
だから、信用できない人のカウンセリングなんて受けられたものじゃない。時間の無駄だ、と
思う。十八年間の記憶を失ったわたしだからこそ、時間を無駄にすることはとてつもない罪悪
であると感じるのだ。
思う。十八年間の記憶を失ったわたしだからこそ、時間を無駄にすることはとてつもない罪悪
であると感じるのだ。
沢崎のカウンセリングルームは、大学から割り当てられた小さな応接室だった。窓が北側に
面しているので、昼間でも薄暗い。部屋の暗さとあいまって、外は快晴なのに、沢崎のバーコ
ード頭を見ているだけでじめじめと湿っぽい気分になってくる。
面しているので、昼間でも薄暗い。部屋の暗さとあいまって、外は快晴なのに、沢崎のバーコ
ード頭を見ているだけでじめじめと湿っぽい気分になってくる。
「香坂沙希ちゃん、だったね。こないだのカウンセリングからもうひと月になるんだなぁ。いや
ぁ働いていると時間の過ぎるのはあっという間ですわ、ははは」
ぁ働いていると時間の過ぎるのはあっという間ですわ、ははは」
悪かったわね。
働いてない優雅な学生でね。
いい年をしてね。
「で、どないですか。調子は。相変わらずですか」
「ええ。調子は抜群です。カウンセリングなんて必要ないくらい」
「沙希!」
母があわてて口を挟む。わたしは黙って下を向いた振りをして、沢崎がペンをカルテに走ら
せる筆跡を盗み見ていた。
せる筆跡を盗み見ていた。
『自覚症状はないというものの態度礼節を欠き時に攻撃的』……ふん。医者を変えてよ。そう
したら礼節をわきまえるから。
したら礼節をわきまえるから。
「はい、この光を見て。今度はこっち。うん。OK。いいですよ」
毎度の瞳孔の診察。繰り返される「いいですよ」の言葉。何がいいですよなんだろう。
「沙希は落ち着いていますよ。広い場所にも夜道にも慣れてきたし」
修一が口を挟んだ。
「むしろ落ち着かないのは、ぼくたちの方なんです。彼女の記憶は、戻らないんでしょうか、事
件が解決してからもう半年以上になるというのに」
件が解決してからもう半年以上になるというのに」
「沙希さん、如何ですか。旦那さんはこうおっしゃっていますが」
「旦那じゃないです」
修一がげじげじの眉を曇らせるのを見たい。わたしはわざと意地悪を言う。
「戸籍上はあなたの旦那さんなんですよ」
「でもわたしは結婚した覚えなんてないですから、そんなことを言われても困るんです」
実際のところ、修一に特に不満がある訳ではなかった。いや、彼と結婚した十年前のわたし
は何を考えていたのだろうと不思議には思うのだけれど。好みの顔とはとてもいえない。
は何を考えていたのだろうと不思議には思うのだけれど。好みの顔とはとてもいえない。
修一の年は三十二歳、わたしより三歳半年上である。長身の大男で、顔もどかんとでかくっ
て、一重まぶたの三白眼、あばたの残る浅黒い頬、どんなに地味で真面目なスーツに身を固
めても、やくざにしか見えない。そんな彼は、笑ってしまうことに、市役所で係長をしている。
て、一重まぶたの三白眼、あばたの残る浅黒い頬、どんなに地味で真面目なスーツに身を固
めても、やくざにしか見えない。そんな彼は、笑ってしまうことに、市役所で係長をしている。
真面目な性格ではあるのだ。たぶん。結婚するには理想的な男性なのだろう。わたしが二十
八歳であることを考えると、年齢的にも釣り合いが取れているのだ。十九歳の陸よりもずっと。
わたしの好みは断然、陸だけれど、それはまあ置いておくとして。陸のわたしへの気持ちは
分からないし。ただの幼馴染みの友達だって思っているのかもしれないし。
八歳であることを考えると、年齢的にも釣り合いが取れているのだ。十九歳の陸よりもずっと。
わたしの好みは断然、陸だけれど、それはまあ置いておくとして。陸のわたしへの気持ちは
分からないし。ただの幼馴染みの友達だって思っているのかもしれないし。
問題は、私が十年前に記憶を喪失し、失踪していたために、身体の年齢よりも精神年齢が
はるかに幼い、という点である。わたしには、修一がお父さんに見えてしまうのだ。陸さえもお
兄さん。わたしにとっては。わたしの精神年齢は、十歳とは言わないまでも十五、六歳くらいら
しいのだ。
はるかに幼い、という点である。わたしには、修一がお父さんに見えてしまうのだ。陸さえもお
兄さん。わたしにとっては。わたしの精神年齢は、十歳とは言わないまでも十五、六歳くらいら
しいのだ。
それを何度医者やわたしが説明しても、父母も、修一も、決して理解しようとしない。まるでわ
たしが意図的に記憶を蘇らせようとしていないかのように。
たしが意図的に記憶を蘇らせようとしていないかのように。
それがわたしにはたまらない。
わたしを愛しているならば、どうしてわたしの言葉を信じてくれないのか、と切なく思う。
「沙希、修一さんはお仕事を休んで来てくださっているのよ」
「休む必要なんてないねんよ」
こんな馬鹿馬鹿しい猿芝居のような儀式のために。
「沙希!」
母が声を荒げる。わたしはそっぽを向く。
沢崎がカルテにペンを走らせる。『家族間の不和、変わらず。』
不和じゃない。単に理解し合えていないだけだ。仲が悪いわけじゃない。医者ならもっと厳密
に言葉を使い分けて欲しい。
に言葉を使い分けて欲しい。
そう……「施設」……兵庫県の三田の山奥にあった「輪廻信教」の施設では、先生たちは皆、
もっと敏感で優しくて理解してくれようという気持ちがあった。
もっと敏感で優しくて理解してくれようという気持ちがあった。
七ヶ月前の摘発で、皆逮捕されてしまったけれども。
「修一さん、長い目で見守ることです。彼女は何といっても、十年も輪廻信教の施設に監禁さ
れていたのですから。周りには理解し得ない、被害者の心の傷は深いんです。周りの方のお
苦しみも分かりますが、彼女を支えてあげられるのは、あなたがたしかいないんです」
れていたのですから。周りには理解し得ない、被害者の心の傷は深いんです。周りの方のお
苦しみも分かりますが、彼女を支えてあげられるのは、あなたがたしかいないんです」
「もちろん、分かっています。ぼくは彼女を愛しています。分かってはいるのですが、ときどき
どうしようもなく切なくなって、行方不明になる前の彼女のことを思い出してしまって……」
どうしようもなく切なくなって、行方不明になる前の彼女のことを思い出してしまって……」
修一の声がかすれる。涙ぐんでいるのだろう。
そして、わたしは、男が泣く、というのは好きじゃない。特に、修一のような大男が泣くなんて、
みっともないことこの上ない。
みっともないことこの上ない。
「行方不明になる前のわたし、と今のわたし、はまた違う人間だと思うんだけど。それをわた
しは受け入れて欲しいの。わたしが生きてきたこの十年の年月を否定しないで欲しい」
しは受け入れて欲しいの。わたしが生きてきたこの十年の年月を否定しないで欲しい」
「分かってる、分かってる、すまない、沙希……」
こほん、と沢崎が咳払いをした。
このオッサンは、所詮ドライなのだ。無難に時間が過ぎるのをただ待っているのだ。
カウンセラー向きの性格とはとても言えない。
「で、沙希ちゃん、頭痛の方はどうかね。鎮痛剤はいつも通りに出しておいたらいいのかな」
馬鹿馬鹿しくなってくる。こんな奴の前で涙を見せる修一も修一だ。ホント、アホだ。
わたしは会話を急いで終わらせて、母と修一を急き立て、そそくさと応接室の外に出た。
「沙希、車に乗って一緒に帰るか?」
「ううん。ありがとう、修一。ごめんね、今日は」
「……いや」
「あのセンセイの顔を見るとむかついて、つい余計なことを言ってしまうの。わたし、五限の数
学の授業に出てから帰ります。仕事休んでもらったのに、ホント、ごめん」
学の授業に出てから帰ります。仕事休んでもらったのに、ホント、ごめん」
「いいんだ。暗い道、怖くないか。迎えに来ようか」
「大丈夫!」
わたしは母と修一が乗りこんだプジョーを見送った。母が振り向いて手を振るのが見えたが、
わたしは見えなかったことにして、校舎へ戻った。
わたしは見えなかったことにして、校舎へ戻った。
十月になると、夜が長い。輪廻信教の施設から解放されて、西宮の門戸厄神の自宅に戻っ
てから数ヶ月間、広い場所に出たり、夜道を歩いたりするのが怖かった。
てから数ヶ月間、広い場所に出たり、夜道を歩いたりするのが怖かった。
輪廻の施設では、施設の中だけで全ての生活が営まれ、狭い空間に慣れきっていたのだ。
でも、今はもう平気。大学から三十分ほどの家への徒歩は、夜道でも気持ちのいいちょっとし
たウォーキングだ。
たウォーキングだ。
大学の正門を出ると、学園花通りという桜並木の大きな通りがある。道路を挟んで右手に県
立西宮高校、左手に西宮市立甲陵中学校。どちらも、柄の悪くない、のんびりとして平和な学
校である。上ヶ原という土地柄がいいのだろうか。
立西宮高校、左手に西宮市立甲陵中学校。どちらも、柄の悪くない、のんびりとして平和な学
校である。上ヶ原という土地柄がいいのだろうか。
仁川幼稚園まで歩くと坂に突き当たる。
そこを降りていくのだが、勾配が激しく、踵の高いパンプスだと少し足が疲れる。
坂一帯は松ケ元緑地という名の、ちょっとした森のように豊かな樹々に恵まれた道である。
松ケ元公園という、猫の額ほどの広さの公園もあって、いつも犬や幼児を連れた人が散歩し
ている。
松ケ元公園という、猫の額ほどの広さの公園もあって、いつも犬や幼児を連れた人が散歩し
ている。
さらに、上甲東園一丁目の急な勾配の坂を下る。右手の石垣は、たぶん大きな邸宅の一部
なのだろう。木の枝がうっそうと石垣から垂れ下がるように茂り、草いきれが鼻をつく。思わず
深呼吸してしまう、緑に溢れた美味しい空気。
なのだろう。木の枝がうっそうと石垣から垂れ下がるように茂り、草いきれが鼻をつく。思わず
深呼吸してしまう、緑に溢れた美味しい空気。
甲東園の駅前まで降りてしまうと、ささやかな学生街だ。
焼肉屋、コンビニ、ゲーセン、レンタルCD店、古本屋。震災後に建ったという再開発駅ビル
「アプリ甲東」はレンガ造りの建物で、地下の高級スーパー、ピーコックや、リブロという名の本
屋をわたしたち学生はよく愛用している。
「アプリ甲東」はレンガ造りの建物で、地下の高級スーパー、ピーコックや、リブロという名の本
屋をわたしたち学生はよく愛用している。
本屋に寄ろうとアプリに入りかけたところで、わたしは金色の毛むくじゃらの固まりに気づい
て、足を止めた。
て、足を止めた。
ポメラニアンだ。駅前の街灯につながれている。朝もいた、そういえば。
あ。
昨日もいた。昨日の朝から同じところにつながれているのだ……。
その証拠に、オシッコが道路に流れてしまっている。かわいそうに。
捨てられたのだろうか。
人懐こい犬で、わたしの顔を見ると、きゅんきゅん甘えてきた。わたしはなめらかな毛並みに
思わず指を滑らせた。
思わず指を滑らせた。
「何。お母さんがいなくてさびしいのかな。お母さんはどこかなぁ。お腹すいてるの?」
犬を相手に独り言を言っていたら、人が通りかかったので慌てて立ち上がる。少し迷ったが、
放っておいたら死んでしまうかもしれない。家族が何というか分からないが、電柱から紐を解い
て、連れて帰ることにした。
放っておいたら死んでしまうかもしれない。家族が何というか分からないが、電柱から紐を解い
て、連れて帰ることにした。
線路沿いに南に十五分ほど歩くと、我が家である。我が家。ようやく馴染んできた私の家。
わたしが発見されてから、修一が引っ越してきた。父と母とわたしに囲まれて、マスオさん状
態で暮らしている。
態で暮らしている。
タラちゃんはいないけれども。
わたしのお家。本当に私の家なんだろうか。ときどき、何もかもが芝居で、わたしは心理テス
トの被験者でテストを受けているのではないだろうか、というような疑いが心をよぎる。こんな大
がかりな芝居がある筈はないのだけれども。
トの被験者でテストを受けているのではないだろうか、というような疑いが心をよぎる。こんな大
がかりな芝居がある筈はないのだけれども。
とりあえず犬を自室に隠し、ご飯に鰹節をかけて、水と一緒に与えた。犬はガツガツと食べ
た。よほどお腹がすいていたのだろう。母に飼っていいかどうか相談しなければならないが、う
ちには既に番犬のチビという雑種の大型犬がいる。難癖をつけられそうな気がする。困ったな
ぁ。
た。よほどお腹がすいていたのだろう。母に飼っていいかどうか相談しなければならないが、う
ちには既に番犬のチビという雑種の大型犬がいる。難癖をつけられそうな気がする。困ったな
ぁ。
「どうする? うちに住む? ポメくん。ポメ、あんたの名前はポメにしようか」
早々に夕食と入浴を済ませ、わたしは部屋にこもった。
一人きりの空間が好きだった。
輪廻信教の施設では、集団生活で、四人部屋で暮らしていたから、わたしは孤独を味わった
ことがなかった。
ことがなかった。
施設を出て、両親が泣きながら迎えに来て、
「ここがあんたの部屋よ。十年前からそのままにしてあったんよ」
と自室に通されたとき、わたしは一人きりになる、という孤独感に震え上がってしまったもの
だ。けれど、一人きりになれることの魅力には、すぐに夢中になってしまった。
だ。けれど、一人きりになれることの魅力には、すぐに夢中になってしまった。
記憶がないとはいえ、わたしがわたしであったことには変わりはなく、部屋はわたしの好きな
落ち着いたブルーで統一され、キラキラとした綺麗な小瓶がたくさん飾られて、わたしの気持ち
を和ませてくれた。
落ち着いたブルーで統一され、キラキラとした綺麗な小瓶がたくさん飾られて、わたしの気持ち
を和ませてくれた。
鏡台は大きくて、全身が映る鏡がついている。わたしはナルシストだったのだろうか。きっと
そうだったに違いない。
そうだったに違いない。
それにしても全身が映る鏡があるというのは便利だ。
ふと、わたしは思いついて服を脱ぎ、下着を脱ぎ、全裸になる。
部屋には鍵はついていないけれども、何かあればノックはしてくれる家族たちなので、何をし
ていてもプライバシーは守られるだろうという安心感があった。見ているのは、ポメラニアンの
ポメだけだ。
ていてもプライバシーは守られるだろうという安心感があった。見ているのは、ポメラニアンの
ポメだけだ。
裸で鏡の前に立ち、自分の姿を見つめる。輪廻信教では許されなかった贅沢だ。
くるりと回り、背中からお尻に視線を走らせる。そしてもう一度、正面を向き、乳房と陰部、足
を観察し、最後に自分の顔を見つめる。
を観察し、最後に自分の顔を見つめる。
髪をかきあげて、こめかみからぐるりと後頭部を一周する傷を確かめる。この傷は、今はもう
痛まないけれど、わたしの頭に細い禿の筋を残した。わたしはそれを隠すために、髪を長く伸
ばしている。もともと茶色い髪なのだが、さらにブリーチをして、金髪にしてしまっている。毛先
はシャギーを入れていることもあって、ぱさぱさだ。
痛まないけれど、わたしの頭に細い禿の筋を残した。わたしはそれを隠すために、髪を長く伸
ばしている。もともと茶色い髪なのだが、さらにブリーチをして、金髪にしてしまっている。毛先
はシャギーを入れていることもあって、ぱさぱさだ。
沙希は二十歳くらいに見えるよ、と誰もが言ってくれる。少なくとも二十八には見えないよ。
と。
と。
信じてもいいのかな。
白い肌にはそばかすが散っている。このそばかすはやっかいで、顔だけではなく全身に散っ
ているのだが、このそばかすがわたしを白人めいて見せているらしい。
ているのだが、このそばかすがわたしを白人めいて見せているらしい。
実際、「失礼だけど、沙希って外人?」「ハーフ?」などと時々聞かれる。
そして、わたしが日本人であることや、二十八であることを聞いて、吃驚されてしまう。
十年前のわたしは何を考えていたのだろうか。聞かされた経歴によると、わたしは関学に入
学した年、十八歳で、あの修一の子を妊娠し、学生結婚したという。そして結婚後、流産してし
まったらしい。
学した年、十八歳で、あの修一の子を妊娠し、学生結婚したという。そして結婚後、流産してし
まったらしい。
家を出て修一のアパートに転がり込み、スナックで「ジュディ」という源氏名を使って働いてい
たという。 そして、そこで自分の身分を偽り、在日外国人を名乗っていたことがどうもあだにな
ったらしいのだ。
たという。 そして、そこで自分の身分を偽り、在日外国人を名乗っていたことがどうもあだにな
ったらしいのだ。
詳しいことは記憶にないので分からないが、身元不明の家出人をかき集めていた輪廻信教
に拉致されたのは、そのスナックからの帰り道だったという。
に拉致されたのは、そのスナックからの帰り道だったという。
輪廻信教は、高宮陸の父親である、高宮正利氏が教祖となっていた宗教団体だった。輪廻
信教の教義は、キリスト教の亜流であるらしいが、肉や魚を食べてはいけない。人間は地球を
支配してはいけない。人間は解脱し、全ての生き物を尊重する生物の代表とならなければなら
ない。そんな信念に基づいて作られていた団体だった。と思う。
信教の教義は、キリスト教の亜流であるらしいが、肉や魚を食べてはいけない。人間は地球を
支配してはいけない。人間は解脱し、全ての生き物を尊重する生物の代表とならなければなら
ない。そんな信念に基づいて作られていた団体だった。と思う。
わたしは、輪廻で脳の手術を受けたらしい。手術の麻酔から目覚め、優しい顔のおじさんが
「気分はどうだい?」
と尋ねてきたところから、今のわたしの記憶は始まっている。
しかし、それが何の手術であったのかは、輪廻から開放された今も分かっていない。CTやM
RIの検査を受けても脳に異常はなく、ただ、記憶を失っていること、だけがわたしの脳の障害
だからだ。それから、ときどき起こる偏頭痛。これはたいしたことはない。
RIの検査を受けても脳に異常はなく、ただ、記憶を失っていること、だけがわたしの脳の障害
だからだ。それから、ときどき起こる偏頭痛。これはたいしたことはない。
輪廻の人々を、わたしは恨んではいない。
皆穏やかな人々で、とても優しくしてもらったし、学問をはじめいろんな生活の知恵を教えても
らった。 わたしも早く解脱したいと思っていたけれども、果たせぬうちに輪廻の施設が一斉捜
索を受け、わたしは今の家に戻されてしまったのだ。
らった。 わたしも早く解脱したいと思っていたけれども、果たせぬうちに輪廻の施設が一斉捜
索を受け、わたしは今の家に戻されてしまったのだ。
高宮陸は、子供だったし、輪廻の活動には関わっていなかったということで、書類送検も見送
られた。有難いことだった。陸は、輪廻信教の施設にいた時代から、ずっとわたしの遊び友達
だったから。
られた。有難いことだった。陸は、輪廻信教の施設にいた時代から、ずっとわたしの遊び友達
だったから。
そしてわたしはもとの自分に戻ることを強要され続けている──関学は、わたしの十年前の
学籍を復活させてくれ、受け入れてくれた。
学籍を復活させてくれ、受け入れてくれた。
関学からは他にも、何人かの留学生が、輪廻に拉致されていたので、カウンセリング体制を
整えて、医師を定期的に呼んだり、進級に必要な単位数を減らしたり、かなりきめ細かい対応
をしてくれている。
整えて、医師を定期的に呼んだり、進級に必要な単位数を減らしたり、かなりきめ細かい対応
をしてくれている。
輪廻信教の事件発覚時は、大きな社会問題となったものだ。なにしろ、六十人もの行方不明
者の行方が分かったのだから。
者の行方が分かったのだから。
しかし、中には死んだのではないかという人もいて、陸の父親は今取調べを受けている。
陸はといえば、JR福知山線沿いに住む祖父母の家に世話になっているとのことだ。
もう輪廻には戻れない。そしてわたしが解脱できる日はもう来ない。
それがようやく覚悟できたのは、ごく最近のことである。
けれども、わたしにはどうしても受け入れられないものがひとつだけある。
大学は素敵だ。
外の世界は広くて未知の事柄に溢れている。
両親はうるさいけれどわたしのことを愛してくれている。
そして修一もわたしのことを愛してくれているらしい。
けれども、わたしが受け入れることが出来ないのは、修一という夫の存在なのである。
彼を嫌いな訳ではない。けれども、嫌いではないことと、愛するということの意味はまったく違
う。わたしは修一を愛せない。というよりも、修一が大人すぎて、わたしたちはさまざまな日常
生活の事柄の中で、心が共鳴しあうことがない。何を面白いと感じ、楽しいと感じ、美しいと感
じ、どんなことに不快をおぼえ、快楽をおぼえるか。彼とわたしには共通項があまりにも少なす
ぎるのだ。陸とわたしには共鳴する部分が多いのに。
う。わたしは修一を愛せない。というよりも、修一が大人すぎて、わたしたちはさまざまな日常
生活の事柄の中で、心が共鳴しあうことがない。何を面白いと感じ、楽しいと感じ、美しいと感
じ、どんなことに不快をおぼえ、快楽をおぼえるか。彼とわたしには共通項があまりにも少なす
ぎるのだ。陸とわたしには共鳴する部分が多いのに。
それが修一には伝わっていないらしいのが、不思議でたまらない。
いや、修一も気がついているのだと思う。
ただ、彼はわたしを探し続けた十年間を無駄にするのが厭で、わたしたちの間柄がもとに戻
らない、という厳格な事実に対し目を塞ぎ耳を塞ぎ、受け入れることを拒否しているのだ。
らない、という厳格な事実に対し目を塞ぎ耳を塞ぎ、受け入れることを拒否しているのだ。
彼が尊重しているのは、わたしへの愛ではない。自分自身の過去なのだ。それがわたしには
分かる、だから余計に、わたしは彼を愛することが出来ない。
分かる、だから余計に、わたしは彼を愛することが出来ない。
パジャマを身に着けて、勉強机に向かったとき、ドアがノックされた。
「沙希。沙希」
修一だ。わたしはドアを開けずに怒鳴った。
「何? こんな夜中に」
「開けてくれよ。葡萄を買ってきたから。好きだろう、葡萄」
「こんな夜遅くに食べへんわよ。太るでしょ。何、酔ってるの。やめてよ」
「何もしないってば。陸と飲んできたんだぜ」
「え?」
わたしは耳を疑った。修一は両親同様、陸が輪廻信教の教祖の息子であることについて陸
に偏見を持っている。しかもわたしのいちばんのボーイフレンドということで、どうやら嫉妬して
いるらしいとも思っていた。
に偏見を持っている。しかもわたしのいちばんのボーイフレンドということで、どうやら嫉妬して
いるらしいとも思っていた。
修一と陸。年も離れて利害も一致し得ない二人が、なぜ。
わたしはドアを開けた。酒で真っ赤になった修一が、葡萄の箱を抱えて部屋に転がり込んで
きた。
きた。
「何これ! 贈答用やん。高かったでしょ? もう、酔った勢いで、何をしでかすやら」
「食えよ。今まで十年間、思う存分好きなものを食ったことなんてなかったんだろう」
「そりゃ、家にいるときみたいにはいかなかったけど……葡萄くらい、食べさせてもらえたわ
よ」
よ」
こんな立派な化粧箱入りの葡萄は食べたことがないけれど。
セロファンを開けると、ぷん、と独特の甘い香りがした。一粒だけ、食べちゃおうかな。
わたしはベッドに伸びている修一を放って、台所に行き、つまみ食いをしてから冷蔵庫に葡
萄をしまった。
萄をしまった。
部屋へ戻ると、修一が起き上がって、ベッドに腰掛けていた。わたしは、少し、怖くなった。
「犬、拾ったのか」
「……うん」
「お母さんには言った?」
「……まだ」
「駄目じゃないか。勝手に連れ込んじゃ。チビもいるし、餌代だって散歩だって手間がかかる
んだぞ」
んだぞ」
「わたしの問題でしょ。指図せんとってよ」
「おれの問題でもあるんや。夫婦なんだから」
「夫婦だなんて、本当は思ってないくせに」
「……」
「……陸と、何、話してたの」
「お前の十年間について。あいつはお前の傍にいた、だから聞けると思った」
「陸、何て?」
少し胸の鼓動が早まる。陸はわたしのことをどんな風に思っているんだろう。風のような陸。
漫才師のようでもある陸。そばかすだらけの陸。
漫才師のようでもある陸。そばかすだらけの陸。
「頭のいい子だって言ってたよ。ゆっくり時間をかければ、お前も警戒をだんだん解いていく
だろうって」
だろうって」
「警戒って」
「おれに警戒しているだろう」
わたしは、すうっと血の気がひいていくのを感じた。陸は修一に、わたしの警戒心を解く方法
をアドバイスした。もし、彼がわたしを好きな女の子として見てくれているんだったら、そんなこ
と、するだろうか?
をアドバイスした。もし、彼がわたしを好きな女の子として見てくれているんだったら、そんなこ
と、するだろうか?
しないよね。
しょうがないか。十歳も年上の女に、陸みたいなもてる男が惹かれる訳もないか。
だけどわたしは泣きたかった。
修一に、早く部屋から出て行って欲しかった。
「警戒なんてしてないよ。ジェントルマンでしょう、修一は。公務員やしさ。もう遅いから、寝よう
よ。おやすみ」
よ。おやすみ」
「聞けよ」
「何よ!」
「陸に招待されたんだ。武田尾の陸のじいちゃんがやってる旅館に泊まりに来ないかって」
「武田尾……」
武田尾(たけだお)。そう、確か陸は武田尾に住んでいる、と言っていた。
JR福知山線で、宝塚駅から確か北へ三個目くらいの駅だ。わたしは行ったことがないけれ
ど、想像もつかないくらい田舎なんだぜ、と陸は妙な自慢をしてたっけ。
ど、想像もつかないくらい田舎なんだぜ、と陸は妙な自慢をしてたっけ。
「招待って」
「温泉があるんやってさ。で、おれと沙希と、二人で遊びに来ないかって」
「何で」
「何でって、レジャーやん。武田尾は峡谷で、ええとこらしいぞ。びっくりしてまうって、あいつ言
ってたぜ。超田舎やから」
ってたぜ。超田舎やから」
「ええとこなんはいいんやけどね。何で、わたしと修一が一緒に陸の家に遊びに行かないとい
けないの」
けないの」
「陸はお前の親友なんだろ。で、おれとも親しくなりたいんやってさ」
身体中の力が抜け落ちそうだった。
陸……。陸は、わたしを、女として愛していないのだろうか。
「明後日の土曜に、泊まりに来いって。行けるか?」
「……うん……行くわ」
もう、どうでもよかった。
わたしはいい加減に頷いて修一を部屋から追い出し、ベッドに突っ伏して、泣いた。届かない
陸を思って、ただただ切なく、ひたすらに泣いた。
陸を思って、ただただ切なく、ひたすらに泣いた。
ポメは椅子の上で丸くなって眠っていた。
わたしと修一は、約束どおり、土曜日の昼から武田尾へ向かった。
意外にも、ポメラニアンを飼うことは、両親ともあっさり承諾してくれた。犬好きらしい。なの
で、陸の祖父母にご迷惑をかけてはいけない、と思い、ポメは家に置いてきた。
で、陸の祖父母にご迷惑をかけてはいけない、と思い、ポメは家に置いてきた。
JR宝塚駅と阪急宝塚駅は隣同士にある。宝塚駅は、結構な都会で、阪急百貨店があるし、
宝塚歌劇でも有名な駅だ。
宝塚歌劇でも有名な駅だ。
そこから、JR福知山線の各駅停車新三田行きに乗り、生瀬、西宮名塩、武田尾。六甲山系
を抜けていくので、トンネルが何度も窓の景色をさえぎる。それでも、時間にして、宝塚からほ
んの15分程度。
を抜けていくので、トンネルが何度も窓の景色をさえぎる。それでも、時間にして、宝塚からほ
んの15分程度。
街から山を幾つか越えた武田尾は、とんでもない別世界だった。
駅がトンネルの中にあるのだ。一足外に出ると、明らかに宝塚よりは数度も低い外気が身体
を包む。向かいのホームの壁までドームになった天井にそって、焦茶色の木片がタイル状に
並んでいる。
を包む。向かいのホームの壁までドームになった天井にそって、焦茶色の木片がタイル状に
並んでいる。
そして、ホームに、日本猿がいた!
「ちょっと、猿よ猿!」
「でかいなぁ。野生なんやなぁ〜。餌くれる人を待ってるんじゃないか」
「何か食べるもの、持ってる?」
「ない。変に餌付けしない方がいいかも」
「そっかぁ……」
猿はわたし達の方を凝視していたが、何もくれないようだと見ると、柵を飛び越えてぴょんと
去ってしまった。
去ってしまった。
猿を見送って、わたし達は駅の階段を降りた。むっとし尿の匂いが鼻をつく。
改札には、切符入れがあった。「ご使用済みの切手は、こちらへお入れください」と書いてあ
る。機械化されていないのだ。驚いてしまう。そして案の定、プレハブのようなトイレが悪臭を放
っていた。
る。機械化されていないのだ。驚いてしまう。そして案の定、プレハブのようなトイレが悪臭を放
っていた。
こんなところに配属された駅員さんは気の毒だなぁ。嗅覚がおかしくなりそうだ。
駅を出ると悪臭は嘘のように消えて、代わりに流れる滝の音と、むせかえるような樹木の匂
い、美味しい空気、見事な峡谷が目の前に開けた。
い、美味しい空気、見事な峡谷が目の前に開けた。
「うわぁ……」
「すごいとこやなぁ。おれ、来たことなかった。こんな近くに、こんなとこがあるなんて」
わたし達は西へ進んだ。赤いつり橋が見えた。道路からそこへ渡るには、短いトンネルをくぐ
るようになっていた。積石で組み立ててあるトンネルの中はひときわ空気がひんやりと冷たく、
奥に鉄の檻があり、黄色い電灯が灯っている。夏休みに連れて行ってもらったロンドンの古城
を思いだすような風景だ。
るようになっていた。積石で組み立ててあるトンネルの中はひときわ空気がひんやりと冷たく、
奥に鉄の檻があり、黄色い電灯が灯っている。夏休みに連れて行ってもらったロンドンの古城
を思いだすような風景だ。
トンネルを抜けると、つり橋だった。観光客らしい女の子が三人、つり橋の下を激しい勢いで
流れる水流を眺めている。
流れる水流を眺めている。
『注意 1 重量制限2t
2 車は一台ずつ通ること』
とある。笑ってしまった。
狭いつり橋、いちいち注意書きなんて書かなくても、小さな車が一台通るのがやっとであるこ
とは一目瞭然だ。
とは一目瞭然だ。
「ひゃー、揺れてるよ、修一!」
「ほんまや、揺れてるな」
つり橋に上ると、風でゆらゆらと揺れるのが分かった。修一は、つり橋の中ほどで足を止め、
叫んだ。
叫んだ。
「山、山、山―!山やなぁ!」
「うん。山やね! すっごい」
前を見ても後ろを見ても、緑の山々が連なっている。少しだけ紅葉していて、ほのかに黄色
い木も見える。橋の下にはとどろく水流。無数の大きな白い岩、灰色の岩をぬって、澄んだ水
が勢いよく流れる。ごおぉぉぉ、という水の音が何とも気持ちよい。
い木も見える。橋の下にはとどろく水流。無数の大きな白い岩、灰色の岩をぬって、澄んだ水
が勢いよく流れる。ごおぉぉぉ、という水の音が何とも気持ちよい。
「沙希! 修一さん! いらっしゃい!」
つり橋の向こう岸から、陸が歩いてきた。
「すごいとこやな、陸くん」
「そうでしょう。温泉が湧くんですよ、ここは」
「穴場やねー。こんな近くに。すごいね」
「うん。近すぎて、近所の人は気づかない感じ。だから観光客も、知る人ぞ知る、って感じで、
少ないねん。でも、武田尾の歴史は古いねんで」
少ないねん。でも、武田尾の歴史は古いねんで」
「歴史?」
「まぁ、見てみ」
陸に手を引かれて──わたしはこんな時だけど、どきどきしてしまった──つり橋を渡りきっ
たところに、観光案内の銀の看板があった。
たところに、観光案内の銀の看板があった。
『武田尾温泉 寛永十八年(一六四一)名塩の人武田尾直蔵が発見したと言われ、石炭化水
素を含む単純泉で、西宮随一の泉郷』
素を含む単純泉で、西宮随一の泉郷』
「え。ここ、西宮市になるの?」
「このあたりは入り組んでいるから。神戸市と宝塚市と西宮市と三田市がごちゃごちゃになっ
てるねん」
てるねん」
「あー、でも、市内なんだぁ。信じられない。村、って感じ」
『JR福知山線複線化による路線変更で、武田尾駅がトンネル内に入ったため、JR中心の風
景は変わったが、一方の主役武庫川の流れには時に激しく岩をかむ変化があり、両岸にも渓
谷美が四季折々のうつろいを見せる中で、料理もこの地ならではのものが楽しめ、浴客は遠く
信州の山峡に遊ぶ旅情が楽しめる』
景は変わったが、一方の主役武庫川の流れには時に激しく岩をかむ変化があり、両岸にも渓
谷美が四季折々のうつろいを見せる中で、料理もこの地ならではのものが楽しめ、浴客は遠く
信州の山峡に遊ぶ旅情が楽しめる』
「信州に行くよりもこりゃいいかもしれへんな」
「そうやね。驚いちゃった」
空を見ると、鳥がV字に列を成して飛んでいくのが見えた。空は青いが、オレンジ色のもやが
少しかかっている。夕方が近い。
少しかかっている。夕方が近い。
ライトバンがゆっくりとつり橋の上を渡っていった。怖くないのかなぁ。
「じゃあ、行こうか。ちょっと山を登るよ」
「了解」
泥で滑る石段をはぁはぁ言いながら登り、着いた陸のおじいさんの民宿は、意外にもお洒落
なログハウスという感じだった。
なログハウスという感じだった。
「最近、立て替えてさ」
「おしゃれやねー。びっくり」
「ぼくの趣味で選んでん。お客さん、増えたで。露天風呂もあるし、まぁゆっくりしていって。今
日はお客さん、予約入れてないねん。ご夫婦貸切やで」
日はお客さん、予約入れてないねん。ご夫婦貸切やで」
陸は得意そうだった。
「わ、そりゃどうも、サンキュ。贅沢やなぁ」
「いいなぁ、こんなところに住んでるなんて」
「熊が出たり猪が出たり、いろいろあるけどねー」
「熊ぁー。ひえぇ」
ログハウスに入ると、お祖母さんとお祖父さんが迎えに出て来てくださった。
「こんにちは。お世話になります」
「まぁまぁ、あなたが沙希さん。その節はご迷惑をおかけしまして……」
「おばあちゃん、この場ではもうその話はせんとって」
「でも陸、あんたのお父さんが、皆さんにご迷惑をおかけしたんやで。わたしらはね、世間様
に顔向けが出来んと思ってます。でも、皆さんご親切に、ご両親には関係ないっておっしゃって
くださって、ご近所さんのお陰で、何とか商売やれてますねん」
に顔向けが出来んと思ってます。でも、皆さんご親切に、ご両親には関係ないっておっしゃって
くださって、ご近所さんのお陰で、何とか商売やれてますねん」
「おばあちゃん。お客さん、足が痺れてまうで。行こう、沙希、修一さん。こっちが部屋です」
通された洋室は、ダブルの広々とした明るい木目の壁の部屋で、調度は欧州カントリー風に
美しく整えてあった。
美しく整えてあった。
そして、窓から、峡谷が一面に見渡せる。赤いつり橋が、おもちゃのように見える。滝の音が
ごおぉぉぉぉ、と耳を澄ませばここまで聞こえてくる。最高だ。
ごおぉぉぉぉ、と耳を澄ませばここまで聞こえてくる。最高だ。
そして、ベッドの下に、金色の大きなゴールデンレトリバーが寝そべっていた。
「わぁ。レトリバーやね。かわいい……」
わたしはホントに犬が好きだ。思わず、手を伸ばす。と、レトリバーは目を開き、賢そうな黒く
濡れた目をわたしに向け、次に修一に向けた。
濡れた目をわたしに向け、次に修一に向けた。
「ヒ―サ―シ―ブ―リ、シ―ュウ―イ―チ……ア―イ―タ―カッータ」
ぎょっとして伸ばした手を引っ込めた。
嘘。
犬が、しゃべった……!?
がたっ、と背後で音がした。振り向くと、修一が荷物を取り落としていた。彼の瞳はわたしを通
り越して、レトリバーを見つめていた。
り越して、レトリバーを見つめていた。
「リ―ク。ム―リ―ヲ―イッ―テ―ゴ―メ―ン―ナ―サ―イ」
「……」
陸を見ると、薄茶色の瞳は不思議な光をたたえて、わたしをまっすぐに見つめ返していた。不
思議な光。悲しみの光? 少し違うような気がする……哀れみ?
思議な光。悲しみの光? 少し違うような気がする……哀れみ?
修一はわたしの方には注意を向けず、ただ、三白眼を怖いほどに見開いて、レトリバーを見
つめている。
つめている。
「……沙希。沙希、なのか。おまえが。沙希……」
「ア―イ―タ―カッ―タ……」
耳の中で滝の音が高まった。鳥がVの字に飛んで行く、金色の空を、ああ、何という吸い込ま
れそうな空。
れそうな空。
そしてわたしは、そのまま倒れてしまったらしい。
輪廻の先生が問いかけていた。
「8×7は分かる?」
わたしは必死で考えて答える。
「分かりません」
「大丈夫。今から教えるから、がんばって覚えようね」
「分からないんです。分からないんです。もう勘弁して」
「大丈夫。きみは奇跡なんだ。覚えのいい頭脳を持ってる。きみは完璧なんだ」
警察官。テレビカメラ。
アナウンサーが叫ぶ。
「たった今、人質達が救出されました。皆、しっかりとした足取りで車に乗り込んでいます」
修一が優しく肩を抱いてくれる。わたしは大きな彼の身体に思わずびくっとする。
「焦らなくていいよ。おびえなくてもいいんだ」
母が言う。
「あんなことさえなければ」
わたしは答える。
「誰も恨んじゃいないわ」
父が言う。
「昔のお前は不良だった。でも、今は良くなった。そう思えば、事件にもいい面もあるってこと
だ」
だ」
私は答える。
「今は良くなったって? これからもずっとお父さんにとってわたしが都合のいい人間であり続
けるという保障があると思う?」
けるという保障があると思う?」
カウンセラーの沢崎が言う。
「今の自分を肯定することが第一歩だよ」
わたしは答える。
「わたしは否定なんてしてません」
修一は酔っている。
「君は変わった」
わたしは答える。
「あんたなんて知らへん」
修一の鋭い血走った瞳がわたしをにらみつける。
「どうして思い出せないんや、沙希」
わたしはにらみ返す。
「どないせえというの。思い出せないものは仕方ないでしょう」
陸は言う。
「何でもさ、あまり気に病まない方がいいよ。ぼくもそうしてる」
わたしは答える。
「気を病んでるのはわたしじゃなくて周りなのよ」
ああ、いつまで答え続ければいいの。わたしはずっと質問されっぱなしだった。ずっと、ずっ
と。
と。
わたしが答える言葉を、みんなは信じてくれたり、信じてくれなかったり。
「信じてよ! わたしはわたしよ! 分からない! やめて! みんな、やめて!!」
「沙希!」
「沙希! ……沙希!」
目を開けると、陸と修一とレトリバーがわたしを覗き込んでいた。
「大丈夫?」
陸が、わたしを助け起こしてくれた。優しい陸の細い腕。けれど、わたしは今日ばかりはとき
めくことが出来なかった。
めくことが出来なかった。
視線が、自然にレトリバーに吸い寄せられてしまう。
黒い瞳。何て濡れて、何て賢明そうな、黒い瞳!
「ワ―ル―イ―ワ―ネ。ヤッ―パ、ショッ―ク―ヨ―ネ」
「沙希、すまない。修一さんには話したんだ、この前飲んだときに。ただ、沙希には──だま
す、とかいう、つもりじゃなかってんけど。ただ、どう言い出したものか、どうしても分からへんで
……」
す、とかいう、つもりじゃなかってんけど。ただ、どう言い出したものか、どうしても分からへんで
……」
陸がわたしを抱え上げて、ベッドに寝かせようとする腕を、わたしは払いのけた。
「修一は知ってたの? 何を? どういうことやの?」
「だから、ポメを拾うのはイヤだったんだ」
「どういうこと? 陸! どういうことよ! 何よ、これは!」
「サ―キ。ホ―ン―ト―ハ、ワ―カッ―テ―イ―ル―ン―デ―ショ―ウ。ア―タ―マ―ノ―イ
―イ、ア―ン―タ―ダ―モ―ノ」
―イ、ア―ン―タ―ダ―モ―ノ」
「誰が頭がいいって? 自分のことを偉そうに言うんじゃないわよ!」
レトリバーにわたしは怒鳴り返し、気がついた。
分かっているんだ。こいつの言うとおり、わたしは、知っていた。
「僕の両親は、生きてるんだ。けど、もう、僕と生活することはない。おそらく、彼らは死刑か
無期懲役は免れない。たくさんの人々を監禁したり殺したりしてしまったから。……僕は両親に
<沙希>を託されたんだ。移植した人間の脳を持つ犬を」
無期懲役は免れない。たくさんの人々を監禁したり殺したりしてしまったから。……僕は両親に
<沙希>を託されたんだ。移植した人間の脳を持つ犬を」
陸が、ぽつり、ぽつり、と話す。
「わたしの脳が、犬に移植されたの? じゃあ、わたしは誰やのよ。犬の脳味噌が中に入って
いるとでも言うの」
いるとでも言うの」
「違うよ、そうじゃない」
「修一。修一は、わたしの脳が、動物実験に使われたって知ってたの……?」
「……」
「知ってたのね」
「……動物実験があったかもしれない、という可能性は報道されていた。だけど、当局の説明
では、移植された人間の脳を持つ動物達は、摘発前に、輪廻信教に皆殺しにされていたという
ことだった。被験者の君たちも、殺されるところだったんや。輪廻信教が、人質として残してい
たおかげで、殺されずに済んだけれど」
では、移植された人間の脳を持つ動物達は、摘発前に、輪廻信教に皆殺しにされていたという
ことだった。被験者の君たちも、殺されるところだったんや。輪廻信教が、人質として残してい
たおかげで、殺されずに済んだけれど」
「それはわたしも覚えてる。仲間たちと、異様な雰囲気の施設の中で脅えていたこと……制
服の警官達が助け出してくれて……あの、あなた」
服の警官達が助け出してくれて……あの、あなた」
何と呼べばいいんだろう。この犬を。
「あなたが、わたしのもとの脳を持ってるの?」
「ソ―ウ―ヨ。モ―ウ―ワ―タ―シ―命―ハ―長―ク―ナ―イ。ダ―カーラ、ヒ―ト―メ―昔
―ノ―自分―ニ―ア―イ―タ―カッ―タ―ノ」
―ノ―自分―ニ―ア―イ―タ―カッ―タ―ノ」
「命?」
「犬の寿命は、十年と少しくらいなんだ。サキはキメラだから、もう少し長く生きられるかもしれ
ないけど、何とも分からなくて」
ないけど、何とも分からなくて」
「キメラって?」
「人間の脳を移植された犬。嗅覚と、人間の世界への溶け込みやすさで、ぼくの両親、輪廻
信教のメンバーは対象を大型犬に絞って、人間の脳を移植する実験を行った。一方で、人間
の臓器を、ES細胞を使って造成する実験も行っていた。その成功例が、沙希、君や。つまり、
君の脳は、君の脳細胞を使って、先端技術で再生された脳なんだ。だから、君はもとの沙希と
同じ脳を持っているし、犬の沙希も沙希の脳を持っている」
信教のメンバーは対象を大型犬に絞って、人間の脳を移植する実験を行った。一方で、人間
の臓器を、ES細胞を使って造成する実験も行っていた。その成功例が、沙希、君や。つまり、
君の脳は、君の脳細胞を使って、先端技術で再生された脳なんだ。だから、君はもとの沙希と
同じ脳を持っているし、犬の沙希も沙希の脳を持っている」
「……やめてよ」
「沙希?」
わたしは、ヒステリーだと分かっていても、犬のサキに怒鳴らずにはいられなかった。
「やめてよ、気味が悪いったら! わたしは、わたしよ。あんたに何の義理があるってのよ。
犬になっちゃったんだったら、犬として生きなさいよ! わたしにはわたしの生活があるんだか
ら!」
犬になっちゃったんだったら、犬として生きなさいよ! わたしにはわたしの生活があるんだか
ら!」
「キッ―ト―ソ―ウ―イ―ウ―ト―思ッ―テ―タ。ア―ン―タ―ッテ、自分―ノ―コ―ト―シ―
カ―考―エ―ナ―イ―女―ダ―モ―ン。最低。現実―ヲ―ミ―ツ―メ―ナ―サ―イ―ヨ」
カ―考―エ―ナ―イ―女―ダ―モ―ン。最低。現実―ヲ―ミ―ツ―メ―ナ―サ―イ―ヨ」
「キャンキャン吠えないでよ!」
陸が叫んだ。
「修一、やめろ!」
振り返ると、修一が、ナイフを持って立ちつくしていた。わたしは慌てた。大男の修一が暴れ
たら、止められる力のある者は誰もいないだろう。
たら、止められる力のある者は誰もいないだろう。
「……もう、やめてくれ。気が狂いそうだ」
「ちょっと、やめなさいよ!」
わたしは、修一とサキの間に立ちはだかってしまった。
「殺さないでよ、仮にもコイツはわたしなんだから!」
修一は、あっけなくナイフを取り落とした。
「気が狂いそうだよ、沙希」
「え?」
修一が話しかけたのは、わたしにではなかった。彼は、犬のサキを抱きしめたのだった。
「沙希! 沙希! 会いたかった……どんな姿でも、どれだけ会いたかったか! ああ!」
「修一、……ゴ―メーン―ネ」
「君は僕のことを覚えていたか? ずっと覚えていたか?」
「忘―レ―タ―コ―ト―ナ―ン―テ、ナ―カッ―タ。ダ―ケ―ド―ワ―タ―シ―ハ―犬―ニ―
ナッ―テ―シ―マッ―タ。モ―ウ、人間―ノ―女―ト―シ―テ―ハ―愛―サ―レ―ナ―イッ―
テ―オ―モッ―タ。都会―ニ―モ―戻―リ―タ―ク―ナ―カッ―タ―ノ。犬―ノ―五感―ガ、自
然―ノ―中―デ―生―キ―タ―イート―願ッテ……、デ―モ、ア―ナ―タ―ノ―コ―ト―ヲ―忘
―レ―タ―コ―ト―ハ―ナ―カッ―タ―ノ。今―デ―モ―好―キ―ナ―ノ、修一」
ナッ―テ―シ―マッ―タ。モ―ウ、人間―ノ―女―ト―シ―テ―ハ―愛―サ―レ―ナ―イッ―
テ―オ―モッ―タ。都会―ニ―モ―戻―リ―タ―ク―ナ―カッ―タ―ノ。犬―ノ―五感―ガ、自
然―ノ―中―デ―生―キ―タ―イート―願ッテ……、デ―モ、ア―ナ―タ―ノ―コ―ト―ヲ―忘
―レ―タ―コ―ト―ハ―ナ―カッ―タ―ノ。今―デ―モ―好―キ―ナ―ノ、修一」
わたしは、今まで、どうしても香坂修一を愛した理由が分からなかった。
「僕も君が好きだ……姿なんて関係ない……君を探していた、沙希。君を愛してる」
けれど、今、彼のことを愛した理由が分かったような気がする。
二人の間にどんなドラマがあったのかは分からない。
けれど、修一のこの奇怪なまでに一途な純愛を、昔のわたしはきっと愛したのだ。
「ダ―メ―ヨ、ホ―ラ、沙希―ガ―妬―イ―テ―ル……」
修一はわたしを振り返った。今はじめて、わたしの存在を思い出したかのように。というより
も、本当にわたしのことなんて今の今まで頭からすっぽり抜け落ちていたのだろう。直情径行
のこの男は。
も、本当にわたしのことなんて今の今まで頭からすっぽり抜け落ちていたのだろう。直情径行
のこの男は。
ああ。涙なんて見せたくない。わたしは涙まみれの顔を手で覆う。
「嫉妬なんて、してないもん……」
そして、わたしが、彼のことを愛さなかった理由も、分かった。
それは、やっぱり、彼が愛していたのは、わたしではなかったからだ。
修一はわたしから目を離し、犬のサキを抱きしめ、肩を震わせて泣いていた。
わたしも泣き続けた。たまらなく、切なかった。右肩に、温かいぬくもりを感じた。陸だった。陸
はわたしの顔を悲しげに覗きこんでいる。
はわたしの顔を悲しげに覗きこんでいる。
そのとき、わたしには理解できてしまったのだ。陸が本気でわたしのことを愛してくれているこ
とを。そして──なんてことだろう、わたしは陸を愛しているかどうか分からなくなってしまってい
ることも。
とを。そして──なんてことだろう、わたしは陸を愛しているかどうか分からなくなってしまってい
ることも。
なんてこと。
修一の馬鹿。
+―+―+―+―+―+―+―+―++―+―+―+―+―+―+―+―+
あれから二年が経つ。
わたしと修一は、二人して陸と犬の沙希の暮らすペンションに住み着いてしまった。武田尾の
峡谷から、わたしと陸は関学へ通い、修一は市役所へ通勤している。
峡谷から、わたしと陸は関学へ通い、修一は市役所へ通勤している。
わたしは彼との離婚届を役所に提出した。
陸はわたしを愛してくれている。
けれど、二年が経っても、わたしの気持ちは修一への不可思議な想いに揺れていて、陸とき
っちり恋人同士になることに踏み切れずにいる。周りの級友たちはそうは見ておらず、わたしと
陸は表向き恋人同士にされてしまってはいるけれど。そして、たぶん、わたしはいつか、遠くな
い未来に、陸の愛情を受け入れるような予感がしているけれども。
っちり恋人同士になることに踏み切れずにいる。周りの級友たちはそうは見ておらず、わたしと
陸は表向き恋人同士にされてしまってはいるけれど。そして、たぶん、わたしはいつか、遠くな
い未来に、陸の愛情を受け入れるような予感がしているけれども。
修一はといえば、どこまで酔狂なのか。今も犬の沙希一筋に熱を上げている。
犬の沙希は自分の寿命が心配だ、なんてのたまっていたけれど、ちゃっかりしたもので、元
気いっぱいだ。わたしは勘ぐってしまう。恋人としての二人の性生活はどうなっているんだろう。
と、陸や修一に尋ねてみると、頭をはたかれてしまうのだけれども。
気いっぱいだ。わたしは勘ぐってしまう。恋人としての二人の性生活はどうなっているんだろう。
と、陸や修一に尋ねてみると、頭をはたかれてしまうのだけれども。
大男の修一と金色のサキとが、峡谷の中、たとえば月夜の晩に、仲良くよりそうふたつの背
中は、まるで童話の絵のようだ。ああ。……
中は、まるで童話の絵のようだ。ああ。……
月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際に、落ちてゐた。
中也の詩に負けないほどに、それは幻想的な風景。
やっぱり、悔しい。そんなとき、わたしはひとつだけ、意地悪なことを考えて、気持ちを紛らわ
せる。
せる。
サキに葡萄は味わえない。サキ本人が悔しそうに言っているので間違いない。
いちばん美しい季節の秋に、誰よりも愛する人とふたり、奔流の音を聞きながら月を眺める
ことは出来るけれど、犬のサキの味蕾は、葡萄の酸味を敏感に感じることは出来ないのだ。
ことは出来るけれど、犬のサキの味蕾は、葡萄の酸味を敏感に感じることは出来ないのだ。
わたしはひとり、時には陸とふたりで、あいかわらず秋には毎日のように葡萄を食べる。
そうして冴え渡る澄んだ空気の中、ひときわ星の煌きが美しい武田尾の豪華な夜空を、ぼん
やりと眺めるのだ。
やりと眺めるのだ。
そんな夜は、心の傷がひときわ切なく痛む。
それはたぶん、死ぬまで忘れられない愛の喪失の記憶。
わたしは甘酸っぱい葡萄を口に含む。そして切なくかみ締める。
<おわり>
(2001・12.04 初稿)
(2002.10.15 改稿)