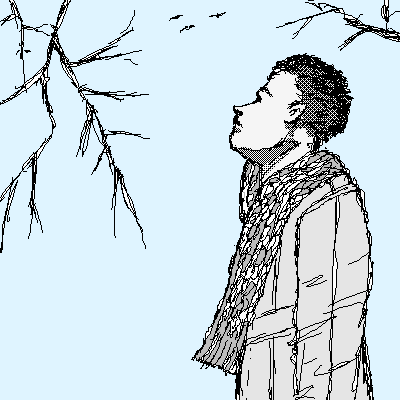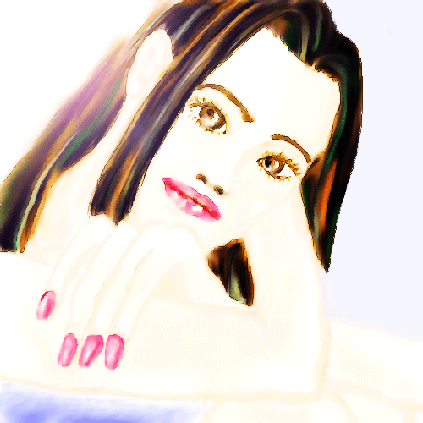
彼女は十八歳にして他人の死が歓びになり得ることを知った。彼女が知った
のは、自分の手を汚して殺したいほどの切実な憎しみではない。ただ、目障り
なものが自分の世界から消滅した、という陰鬱な快感だった。戦地の子供なら
ば五歳でその陰鬱な歓びを知っているかもしれないと思ってみるなら、十八歳
まで知らずに生きることが出来た自分は幸せなのかもしれない、と彼女はぼん
やりと感じてもいた。二十二歳になったとき、彼女が他人の死を歓びと感じた経
験は三度に達していた。一人は高校時代の担任。一人は自分の父親。一人は
恋敵だった。正確には高校の担任は自殺未遂で重症を負い休職したのだった
が、彼女の中では同じことだった。自分の目前から消えてくれれば、それでよか
った。
のは、自分の手を汚して殺したいほどの切実な憎しみではない。ただ、目障り
なものが自分の世界から消滅した、という陰鬱な快感だった。戦地の子供なら
ば五歳でその陰鬱な歓びを知っているかもしれないと思ってみるなら、十八歳
まで知らずに生きることが出来た自分は幸せなのかもしれない、と彼女はぼん
やりと感じてもいた。二十二歳になったとき、彼女が他人の死を歓びと感じた経
験は三度に達していた。一人は高校時代の担任。一人は自分の父親。一人は
恋敵だった。正確には高校の担任は自殺未遂で重症を負い休職したのだった
が、彼女の中では同じことだった。自分の目前から消えてくれれば、それでよか
った。
彼女は自分のことを、少しだけ負けん気が強い、そしてそれなりに美しい、至
極平凡な女だと捉えている。
極平凡な女だと捉えている。
新緑の季節を過ぎて、六月の木々の緑が爽やかな空気の中、目にますます
眩しい。朝練をするテニス部の生徒の高らかな掛け声が、黄色いボールがクレ
ーコートにポーンと弾む小気味良い音とともに、校内に響き渡っている。
眩しい。朝練をするテニス部の生徒の高らかな掛け声が、黄色いボールがクレ
ーコートにポーンと弾む小気味良い音とともに、校内に響き渡っている。
S市立八木田高校は、駅からの勾配が厳しい、坂の上にあった。
朝、七時十五分。祖牧水絵(そまき みずえ)は、半袖の紺のスーツに身を固
め、急な坂を自転車で一気にこぎ上がり、八木田高校の正門へ到着した。細い
小柄な身体、健康的な薔薇色の肌に、毛先をシャギーにした黒髪がなびく。す
っきりと伸ばした背筋は野生の子馬を思わせる。若さと生命力の塊のような娘
である。
め、急な坂を自転車で一気にこぎ上がり、八木田高校の正門へ到着した。細い
小柄な身体、健康的な薔薇色の肌に、毛先をシャギーにした黒髪がなびく。す
っきりと伸ばした背筋は野生の子馬を思わせる。若さと生命力の塊のような娘
である。
八木田高校は、三年と少し前まで毎日通った、彼女の母校だった。
今、水絵は再び二週間八木田高校に通うことになった。教育実習生として。
実習生という身分ではあるけれども、教える側として通う立場になったのだ、
という感慨が水絵を捉えた。何よりも、自転車で校内に乗りつけることの出来
る、この快感。高校時代、自転車通学は禁止されていたのだ。最寄り駅までの
交通手段については、バスを使おうと電車を使おうと自転車を使おうと親に車で
送ってもらおうと、バイクさえ使わなければ自由だった。が、最寄り駅からは徒
歩で来るべし、というのが八木田高校の校則だった。水絵は悪友たちと共に、
しばしばこの校則を破った。自転車で高校の近所まで乗りつけ、駐輪出来そう
な場所を見つけて自転車をとめておいたものだった。近所の教会、コンビニエン
スストア、スーパー、マンションなどが格好の自転車置き場だった。一度ならず、
生活指導の教師にお灸を据えられたことがある。ひどい時には、自転車のサド
ルを持って行かれた。サドルのない自転車がずらりと並ぶ側には、ダンボール
の裏に大きくマジックで書かれた看板が、嘲笑うかのようにくくりつけてあった。
という感慨が水絵を捉えた。何よりも、自転車で校内に乗りつけることの出来
る、この快感。高校時代、自転車通学は禁止されていたのだ。最寄り駅までの
交通手段については、バスを使おうと電車を使おうと自転車を使おうと親に車で
送ってもらおうと、バイクさえ使わなければ自由だった。が、最寄り駅からは徒
歩で来るべし、というのが八木田高校の校則だった。水絵は悪友たちと共に、
しばしばこの校則を破った。自転車で高校の近所まで乗りつけ、駐輪出来そう
な場所を見つけて自転車をとめておいたものだった。近所の教会、コンビニエン
スストア、スーパー、マンションなどが格好の自転車置き場だった。一度ならず、
生活指導の教師にお灸を据えられたことがある。ひどい時には、自転車のサド
ルを持って行かれた。サドルのない自転車がずらりと並ぶ側には、ダンボール
の裏に大きくマジックで書かれた看板が、嘲笑うかのようにくくりつけてあった。
『サドルは明日まで保管とする。保管時期を過ぎれば廃棄とする。皆の名前
はこちらで記録しているので必ず取りに来るように。取りに来なかった場合は別
途処分あり。山口』
はこちらで記録しているので必ず取りに来るように。取りに来なかった場合は別
途処分あり。山口』
山口教諭は厳しいことで有名な社会科の名物教師だった。脅えた水絵たちが
集団でサドルを取りに行くと、竹刀で臀部を一発ずつはたかれて、ようやく返し
てもらえたものだ。
集団でサドルを取りに行くと、竹刀で臀部を一発ずつはたかれて、ようやく返し
てもらえたものだ。
それでも、喉元過ぎれば何とやら、で水絵たちは懲りずに自転車通学を繰り
返し、生活指導の教諭たちと激しいデッド・ヒートを繰り広げたものだった。
返し、生活指導の教諭たちと激しいデッド・ヒートを繰り広げたものだった。
それも今は昔、だ。
水絵は自転車を軽やかに校内の駐輪所に止めながら、鼻歌でも出そうな気
分だった。早速、上履きに履き替え、職員室に向かう。まだ、水絵の担当となる
教諭は出勤していなかった。
分だった。早速、上履きに履き替え、職員室に向かう。まだ、水絵の担当となる
教諭は出勤していなかった。
「お! 祖牧やないか」
「あーっ! ……山口先生! おはようございます」
水絵は慌てた。学生時代、散々生活指導を食らった山口教諭が、ジャージ姿
で団扇を片手に目の前に立っていた。
で団扇を片手に目の前に立っていた。
「何や。そうか、教育実習やな。お前もそんな年になったんか」
「ハァ、そうなんです。どうぞよろしくお願いします」
「そうか、まあ座れや」
意外にも親切に、山口教諭は空いた椅子を示し、水絵に座るよう促した。水
絵はおとなしく座った。内心、来るタイミングが悪かった、と自分を呪っていたの
だが。初日だからと張り切って、早く来すぎてしまったようだ。あまり早い時間に
出勤すると、どこの職場でもこういう高血圧タイプの人間が意気揚揚と朝からテ
ンションを上げているものだ。そういえば今のバイト先でもそうだ。水絵はふと可
笑しくなった。
絵はおとなしく座った。内心、来るタイミングが悪かった、と自分を呪っていたの
だが。初日だからと張り切って、早く来すぎてしまったようだ。あまり早い時間に
出勤すると、どこの職場でもこういう高血圧タイプの人間が意気揚揚と朝からテ
ンションを上げているものだ。そういえば今のバイト先でもそうだ。水絵はふと可
笑しくなった。
「最近、どうや」
抽象的な質問だった。水絵は曖昧に微笑んだ。ボチボチですワ、と高校時代
なら答えるところだった。が、それは自粛した。自分も大人になったのだ、と思
う。
なら答えるところだった。が、それは自粛した。自分も大人になったのだ、と思
う。
「そうですね、マイペースでやってます」
「就職は決まったか。教職一本か?」
「ええ」
「正直に言うたらええねんぞ。まあ無理か。教育実習を受ける以上、会社訪問
してるとは言いにくいやろうからな」
してるとは言いにくいやろうからな」
山口教諭は台詞を自己完結させてしまった。こういうところは昔から変わって
いない。 水絵は笑いながら反論した。
いない。 水絵は笑いながら反論した。
「わたしは教職一本でいくつもりなんです。…企業も訪問してますけど、教育
関係ばかりです」
関係ばかりです」
「そうか。科目は何や」
「国語です」
「ああ。じゃ、生田先生につくんか?」
「ええ、そう伺ってます」
「そうか、あの先生はええ先生やぞ」
「そうですか……」
生田教諭は五十代、ベテランの女性教諭だ。八木田高校には二年前に赴任
してきたとのことで、在学中の水絵との面識はない。
してきたとのことで、在学中の水絵との面識はない。
山口教諭と話を交わしているうちに、他の教諭たちも続々と出勤してきた。
「おはようございます」
「暑いですねぇ」
朝の挨拶が飛び交う。
「おはようございます」
車椅子が山口教諭の側を通りかかった。山口教諭に挨拶した車椅子の教師
の顔を見て、水絵は、ぎくりとした。
の顔を見て、水絵は、ぎくりとした。
──帆谷……! まだいたのぉ…?
数学の帆谷寛(ほたに ひろし)教諭は、水絵には気づかなかったようだっ
た。それとも、気づかないふりをしたのか。帆谷の存在は、水絵の中ではすっか
りと消滅したものになってしまっていたが、姿を見れば鮮烈な想い出が蘇る。そ
れは、初めて水絵が人の死を歓んだ経験でもあった。
た。それとも、気づかないふりをしたのか。帆谷の存在は、水絵の中ではすっか
りと消滅したものになってしまっていたが、姿を見れば鮮烈な想い出が蘇る。そ
れは、初めて水絵が人の死を歓んだ経験でもあった。
水絵の中で、帆谷は死人だった。昔散々叱られた山口教諭以上にもっとも再
会したくなかった人物、それが帆谷だった。
会したくなかった人物、それが帆谷だった。
──車椅子を使っているのか…。
帆谷は、水絵が高三の時の学級担任だった。その頃彼は、多少奇妙な歩き
方ではあったが、──帆谷に関する限り、全てが奇矯だった、動作も、話し方
も、授業の内容も、会話の内容も──自力で歩行していた記憶がある。
方ではあったが、──帆谷に関する限り、全てが奇矯だった、動作も、話し方
も、授業の内容も、会話の内容も──自力で歩行していた記憶がある。
それも二学期までだったが。
三学期、冬休みを終えて登校した水絵たちの前に、帆谷は姿を現さなかっ
た。朝のホームルームの時間は、誰も来ないままに過ぎ、そのまま一時間目に
入り淡々といつもと変わらない一日が始まった。六時間目が終わりホームルー
ムの時間になってやっと、担任が顔を出さなかった謎が解けたのだった。
た。朝のホームルームの時間は、誰も来ないままに過ぎ、そのまま一時間目に
入り淡々といつもと変わらない一日が始まった。六時間目が終わりホームルー
ムの時間になってやっと、担任が顔を出さなかった謎が解けたのだった。
ホームルームに姿を現したのは、担任の帆谷ではなく、当時学年主任をして
いた山口教諭だった。
いた山口教諭だった。
「帆谷先生は、残念ながら怪我のため当分学校を休まれることになった。家の
ベランダから落ちられた、とのことなので、重体で、君たちの卒業式にも出られ
るかどうか…」
ベランダから落ちられた、とのことなので、重体で、君たちの卒業式にも出られ
るかどうか…」
山口教諭の声は、教室に沸き起こった歓声にかき消された。水絵も後ろの席
の友人と手を取り合って飛びあがり、喜んだ。
の友人と手を取り合って飛びあがり、喜んだ。
「やったァー!」
「ィヤッホォー!」
「死ね、死ね〜!」
「どんくせぇー」
「くっさいなぁ!」
「ベランダって自殺ちゃうんかぁ?」
「もっとはよ死ねば良かったのに」
「まだ死んでへんって」
「あ、そっかー、殺してもうたがな」
「ハハハハ」
止むことのない悪童たちの歓声は、山口教諭が教壇をこぶしで叩いたことで
一瞬静まった。
一瞬静まった。
「お前ら……」
山口教諭は言葉が出ない様子だったが、何とか先を続けた。
「お前らには人の心があらへんのか。覚えとけ、今笑ったヤツは一生後悔す
んぞ」
んぞ」
190センチの身長を誇る柔道部の曽我部が立ち上がって山口教諭の口調を
真似た。
真似た。
「聞いたかぁ? 覚えとけ、今笑ったヤツは一生後悔するってよー。おー、怖ぇ
〜」
〜」
「ギャハハハハハ!」
その時笑った連中の中に、水絵がいたことは、山口教諭はもう覚えていない
かもしれないが──何しろクラスのほぼ全員が笑っていたのだから──水絵自
身は覚えている。
かもしれないが──何しろクラスのほぼ全員が笑っていたのだから──水絵自
身は覚えている。
「一生後悔するなんて、言われても、なァ。相手が帆谷やから、しゃあないわ
なァ。自業自得やん」
なァ。自業自得やん」
と、あとで友人に言ったものだ。
けれど、山口教諭のあの時の台詞は正しかったのかもしれない。現に今、水
絵は帆谷教諭を現役時代苛めたことについて、かなり後悔し始めていた。とい
うよりも、帆谷との思わぬ腐れ縁を呪っていた、という方が正確か。
絵は帆谷教諭を現役時代苛めたことについて、かなり後悔し始めていた。とい
うよりも、帆谷との思わぬ腐れ縁を呪っていた、という方が正確か。
──これから二週間かぁ。どこかで帆谷と鉢合わせたらどないしよう。気まず
いよなぁ…。
いよなぁ…。
「祖牧さん?」
気がつくと、これから水絵の指導担当教諭となる生田教諭が、クラス名簿を胸
に抱えて水絵の顔を覗き込んでいた。
に抱えて水絵の顔を覗き込んでいた。
「あっ、生田先生! おはようございます! これからよろしくお願いしま
す!」
す!」
「いえこちらこそどうも。まず、最初はわたしの授業を見学してもらいます。見
学するときは、座らないで、立っているようにお願いしますね。教師というのは
立ちっ放しの仕事ですから。それから、指導要領案を提出してもらって、OKだと
こちらが判断したら、授業をしてもらいますが、気をつけてもらいたいのは、…
…」
学するときは、座らないで、立っているようにお願いしますね。教師というのは
立ちっ放しの仕事ですから。それから、指導要領案を提出してもらって、OKだと
こちらが判断したら、授業をしてもらいますが、気をつけてもらいたいのは、…
…」
生田教諭はなかなか厳格な教諭のようだった。水絵は多少緊張しながら、神
妙な表情を作って頷いていたが、内心では意識は半分帆谷の上にあった。
妙な表情を作って頷いていたが、内心では意識は半分帆谷の上にあった。
水絵たち三年五組の生徒は、徹底的に、新任三年目の帆谷教諭をほぼ全員
で苛めたのだ。苛めに加わらなかった生徒は、一部の温厚な男子生徒のみだ
った。女子生徒は皆が皆、帆谷を嫌った──どんなおとなしい子でも、帆谷を見
ると顔をしかめた。生理的に受け付けない異性に対する本能的な嫌悪感が、最
も過敏に働く年頃だった。
で苛めたのだ。苛めに加わらなかった生徒は、一部の温厚な男子生徒のみだ
った。女子生徒は皆が皆、帆谷を嫌った──どんなおとなしい子でも、帆谷を見
ると顔をしかめた。生理的に受け付けない異性に対する本能的な嫌悪感が、最
も過敏に働く年頃だった。
帆谷。思えば気の毒な人間だったのだ。けれど、──未だに水絵は思う──
数学の授業が帆谷にさえ当たらなければ、文系ではなく理系に行けたり、浪人
せずに済んだりした生徒は二百人はくだらないのではあるまいか。
数学の授業が帆谷にさえ当たらなければ、文系ではなく理系に行けたり、浪人
せずに済んだりした生徒は二百人はくだらないのではあるまいか。
運の悪いことに、数学は一年の時からずっと水絵は帆谷の授業に当たった。
それでなくともつまずく場合の多い難解な高校の数学は、帆谷のお陰で水絵に
とってはチンプンカンプンの分野になってしまった。
それでなくともつまずく場合の多い難解な高校の数学は、帆谷のお陰で水絵に
とってはチンプンカンプンの分野になってしまった。
帆谷という教師は、水絵から見れば、男としてもとんでもない奴だった。
まず、見る者に嫌悪感を抱かせずにはいられないその容姿。180センチはあ
ろうかと思われる長身だったが、体重はといえば60キロあるかどうかも疑問
で、骸骨のように痩せていた。顔色は真っ青、斜視でワシ鼻、髪は若いくせに
べっとりとした七三分け。ヒットラーを限りなくみすぼらしくしたらこうなるだろう、
とでも言いたくなるような悪人面だった。
ろうかと思われる長身だったが、体重はといえば60キロあるかどうかも疑問
で、骸骨のように痩せていた。顔色は真っ青、斜視でワシ鼻、髪は若いくせに
べっとりとした七三分け。ヒットラーを限りなくみすぼらしくしたらこうなるだろう、
とでも言いたくなるような悪人面だった。
だが、容姿だけなら、帆谷よりひどい顔の教師はたくさんいた。帆谷はみすぼ
らしかったが若かった分、ふためと見れないグロテスクな姿とまではいかなかっ
た。といっても、水絵たちは『気色悪〜!』と聞こえがしに言っていたものだった
が。
らしかったが若かった分、ふためと見れないグロテスクな姿とまではいかなかっ
た。といっても、水絵たちは『気色悪〜!』と聞こえがしに言っていたものだった
が。
何よりも最悪なのは、授業の内容だった。
帆谷の授業は、単に、用意してきた講義プリントをつっかえながら棒読みす
る、というだけのものだった。たった一行読むのに何度も何度も何度も何度も何
度も……一行につき数回はどもったり間違えたりするので、講義プリントを音読
して中の公式や例題を時々板書する、というだけの動作で五〇分間の授業は
あっという間に終わってしまうのである。聞いているほうがノイローゼになってし
まいそうな話ぶりだった。実際、帆谷が教室を出たあとは、皆がわらわらと窓辺
や廊下へ散って、新鮮な空気を求めたものだ。真面目に勉強したいと思ってい
る者も、そうでない者も、気が狂いそうな、フラストレーションのたまる授業だっ
た。
る、というだけのものだった。たった一行読むのに何度も何度も何度も何度も何
度も……一行につき数回はどもったり間違えたりするので、講義プリントを音読
して中の公式や例題を時々板書する、というだけの動作で五〇分間の授業は
あっという間に終わってしまうのである。聞いているほうがノイローゼになってし
まいそうな話ぶりだった。実際、帆谷が教室を出たあとは、皆がわらわらと窓辺
や廊下へ散って、新鮮な空気を求めたものだ。真面目に勉強したいと思ってい
る者も、そうでない者も、気が狂いそうな、フラストレーションのたまる授業だっ
た。
帆谷は、舌に障害があるようだった。吃音(どもり)がはげしかったのだ。動作
も非常にぎごちなく、ひょろ長い手足をもてあましたロボットのようで、動きがカク
カクとしていた。もちろん彼に雑談などする芸当はなかった。
も非常にぎごちなく、ひょろ長い手足をもてあましたロボットのようで、動きがカク
カクとしていた。もちろん彼に雑談などする芸当はなかった。
一度、彼に比較的同情的だった男子生徒が、
「先生、彼女おるん?」
と聞いたことがある。
「そ、それは、え、え、エッチもしたいのはみんな、お、同じやからな」
クラス全員が水をうったように静まり返った。
その後、『エ、エ、エッチ』が三年五組の流行語になったのは言うまでもない。
しかし、水絵たちにとっては冗談や気色悪いだけで済ませられる問題ではな
かった。
かった。
数学が分からないのだ。
帆谷のせいで!
帆谷の授業を聞いているくらいなら、漫画の本でも読んでいた方がよほどため
になると思えた。水絵たちのクラスは、センター試験受験組の、入試科目の中
に数学が入っている大学を目指す生徒がほとんどだったので、水絵たちは帆谷
の無能に本気で怒った。
になると思えた。水絵たちのクラスは、センター試験受験組の、入試科目の中
に数学が入っている大学を目指す生徒がほとんどだったので、水絵たちは帆谷
の無能に本気で怒った。
だが、帆谷は無能なだけで、授業は真面目に行っている。いっそ、不真面目
な方が校長なりへの直談判も出来て良かったのかもしれない。だが、時間をき
っちり守り、カリキュラムも、形式上はスケジュール通りこなす帆谷に正面から
の攻撃を加えることは難しかった。
な方が校長なりへの直談判も出来て良かったのかもしれない。だが、時間をき
っちり守り、カリキュラムも、形式上はスケジュール通りこなす帆谷に正面から
の攻撃を加えることは難しかった。
そうして、水絵たちの行き場のない怒りは、やがて帆谷への強烈な苛めへと
昇華していったのだ。
昇華していったのだ。
帆谷が板書をする時に、交代で、あらかじめかっぱらってあったチョークを黒板
に投げる。皆が笑う。
に投げる。皆が笑う。
「い、今投げたのはだ、誰や」
何度かは我慢していた帆谷がたまりかねて振り返って聞くと、
「だ、だ、誰やー」
「いいいいまなななげたのはー」
と、生徒たちは帆谷の吃音を口々に真似て嘲笑った。無論クラスの中でも気
が強い方だった水絵も、チョークを投げたし、大声で口真似もした。帆谷もそれ
は気付いていたと水絵は思う。
が強い方だった水絵も、チョークを投げたし、大声で口真似もした。帆谷もそれ
は気付いていたと水絵は思う。
昼食の時間、帆谷は教壇で弁当を食べていたものだったが、水絵は面白がっ
てそのお茶のコップの中にチョークの粉を入れたこともあった。トイレで手を洗っ
て戻ってきた帆谷は、それと知りながら黙々とピンク色に染まったお茶を飲み干
し、水絵たちはどっと喝采した。
てそのお茶のコップの中にチョークの粉を入れたこともあった。トイレで手を洗っ
て戻ってきた帆谷は、それと知りながら黙々とピンク色に染まったお茶を飲み干
し、水絵たちはどっと喝采した。
そんな日々が続いた冬、帆谷は自宅のベランダから落ちたのだ。
落ちたのは事故ではなく自殺未遂にちがいない、という意見と、お陰で数学の
担当が変わって入試までの少しの期間でも有難い、という意見が、三年五組の
概ねの統一見解だった。
担当が変わって入試までの少しの期間でも有難い、という意見が、三年五組の
概ねの統一見解だった。
ベランダから落ちた、というニュースに馬鹿笑いし、帆谷という名前は水絵た
ちの記憶からはすっかり消え去った。目前の入試、卒業、進学と、水絵たちの
前に開ける道は広かった。複雑に入り組んだ人生の分岐点だった。
ちの記憶からはすっかり消え去った。目前の入試、卒業、進学と、水絵たちの
前に開ける道は広かった。複雑に入り組んだ人生の分岐点だった。
教師についてのそんな厭な記憶もあったが、水絵は教職に就きたいと希望し
ていた。
ていた。
大学に入学して以来、水絵はずっと学習塾で講師のアルバイトを続けてい
た。
た。
講義には慣れていたので、教育実習に対しての緊張はなかった。
生田教諭がどの程度の話し上手かは知らないが、公務員である市立学校の
教諭よりは、民間で鍛え上げられた自分の方が授業は上手いかもしれない、と
の驕りめいた自信さえもあった。
教諭よりは、民間で鍛え上げられた自分の方が授業は上手いかもしれない、と
の驕りめいた自信さえもあった。
実習に入ってからの水絵の講義は予想通りスムーズに進んだ。
「あなた、話慣れてるわね。そうね……あとは、板書の字が少し丸いのを何と
かして頂戴。それさえ直れば、まあ必要な点は抜かしていない講義でしたね」
かして頂戴。それさえ直れば、まあ必要な点は抜かしていない講義でしたね」
厳しい生田教諭から及第点が出た。
水絵は心ならずも、ほっと胸を撫で下ろした。
生田教諭は、水絵が教壇に立っている間、決して口出しをしない。起立から礼
まで、水絵の独壇場にさせている。そして、教室の後ろにすくっと立って背筋が
寒くなるほどの鋭い視線で水絵を睨みすえているのだ。どんなあら捜しをされて
いるのだろう、と脅えていたが、案外柔らかな批評に安堵した。が、生田教諭の
冷徹な視線に耐えるべく、水絵は翌日から、より地味な化粧を心がけた。
まで、水絵の独壇場にさせている。そして、教室の後ろにすくっと立って背筋が
寒くなるほどの鋭い視線で水絵を睨みすえているのだ。どんなあら捜しをされて
いるのだろう、と脅えていたが、案外柔らかな批評に安堵した。が、生田教諭の
冷徹な視線に耐えるべく、水絵は翌日から、より地味な化粧を心がけた。
そしてやっと土曜日が来た。大人びた高校生たちと生田教諭の鋭い視線が
全身に突き刺さる中、緊張の続く、長い一週間だった。
全身に突き刺さる中、緊張の続く、長い一週間だった。
帆谷には毎朝すれ違ったが(彼の車椅子姿が目立つので、無視したくても気
づかずにはいられなかった)水絵はついに挨拶出来ずじまいだった。
づかずにはいられなかった)水絵はついに挨拶出来ずじまいだった。
教師生徒の関係ではなく、先輩後輩の間柄になると、不思議なもので、帆谷
に対する昔の嫌悪感は消えた。
に対する昔の嫌悪感は消えた。
水絵は帆谷にも普通に接したかったのだが、自分の昔の悪童ぶりと帆谷の
自殺未遂を思うと、到底、なにごともなかったように接するような厚顔さは持てな
かった。
自殺未遂を思うと、到底、なにごともなかったように接するような厚顔さは持てな
かった。
塾のアルバイトの方は、教育実習期間中休みを取っていたが、土日は休みを
取っていなかった。水絵は小学五年生のクラスを担当していた。生徒は高校生
と比べると段違いに可愛かった。水絵はアルバイトを休まなくて正解だったか
な、と思いながら土曜の晩の授業を始めた。
取っていなかった。水絵は小学五年生のクラスを担当していた。生徒は高校生
と比べると段違いに可愛かった。水絵はアルバイトを休まなくて正解だったか
な、と思いながら土曜の晩の授業を始めた。
今、受け持っている高校生との年齢差で考えれば、ほんの六、七歳の差。そ
れがこんなに人間を変えるのか、と改めて思う。自分のひとことひとことに対す
る生徒の反応が、熱気が、違う。小学五年といえば、騒ぎたくて仕方ない年頃
である。水絵は彼らに負けじと声を張り上げながら、チョークが黒板をカツカツと
なぞる音さえも響き渡る静けさの高校での授業風景を思い浮かべ、そのギャッ
プに今更ながら面食らう思いだった。
れがこんなに人間を変えるのか、と改めて思う。自分のひとことひとことに対す
る生徒の反応が、熱気が、違う。小学五年といえば、騒ぎたくて仕方ない年頃
である。水絵は彼らに負けじと声を張り上げながら、チョークが黒板をカツカツと
なぞる音さえも響き渡る静けさの高校での授業風景を思い浮かべ、そのギャッ
プに今更ながら面食らう思いだった。
ふと、下腹部に鈍痛が走った。
水絵は教壇のかどに捕まった。
「先生、どないしたん?」
「や、待って……あぁ……あーっ!」
身体中の血がすうっとひいていった。
水絵は意識を失って倒れた。
すぐに気がついたようで、目を開くと、幼い顔たちが水絵を不思議そうに覗き
込んでいた。
込んでいた。
下腹部が痛い!
「インターフォンを押して! 坂口君! 早く! 先生が倒れているって言っ
て!」
て!」
薄れそうになる意識の中で、水絵は必死に生徒に指示を出した。原因は分か
っていた。
っていた。
生理痛である。
もともと生理は重かった。授業前に鎮痛剤を飲んだのだが、効かなかったよう
だ。こんな悪寒をもよおす酷い生理痛が年に一、二度の割合である。だが、授
業中に気が遠くなったのははじめての経験だった。
だ。こんな悪寒をもよおす酷い生理痛が年に一、二度の割合である。だが、授
業中に気が遠くなったのははじめての経験だった。
すぐに救急車が到着した。
「どうしました? 意識はありますか?」
救急隊員が声をかけてきた。
意識はあったが、答えることが出来なかった。いっそ消えてしまいたいくらい
痛みは酷く、痛み以外の身体の感覚が麻痺してしまっていた。
痛みは酷く、痛み以外の身体の感覚が麻痺してしまっていた。
「お腹が痛いんですね? 他に痛いところはありませんか?」
顔を両手で覆い、弱々しく首を振る。
──苦しい。苦しい。お母さん。誰か。助けて……生理痛だなんて言えないし
……。
……。
こうして救急車で運ばれた経験も一度や二度ではなかった。用心はしても、子
宮が水絵を裏切ることはよくあった。鎮痛剤でも効かないなら、倒れて病院に運
んで強い薬を打ってもらうしかなかった。
宮が水絵を裏切ることはよくあった。鎮痛剤でも効かないなら、倒れて病院に運
んで強い薬を打ってもらうしかなかった。
サイレンの音がやんだ。病院に到着したのだ。
「祖牧さん! 聞こえますか? 着きましたよ! 分かりますか?」
「ハイ……あの、ごめんなさい、生理なんです私……」
言った途端に、喉元に込み上げるものがあった。水絵は激しく嘔吐した。
「す、すみません……うぐっ!」
「ああ、いいから、いいから。大丈夫ですか? いつもこんなに重いの?」
「……鎮痛剤は……飲んだんですけど、効かなくて……」
「そうかね。座薬ならよく効くよ。入れますよ」
水絵が何も言えないでいる間に、水絵のスカートはめくられて、下着を下げら
れ、尻を広げられて、肛門に冷たい座薬がすべりこんできた。
れ、尻を広げられて、肛門に冷たい座薬がすべりこんできた。
そんな中なのに、水絵は消防隊員がごくっと唾を飲む音を聞いた。
何もかもが突然の屈辱だった。
痛みと屈辱が水絵を打ちのめしていたが、母親が知らせを聞いて駆けつけた
頃には、座薬の効果で痛みは嘘のように治まっていた。
頃には、座薬の効果で痛みは嘘のように治まっていた。
土曜のアルバイト代は、この場合、教師が授業を故意または過失に当日放棄
したという咎で、給料から一万円差し引かれる仕組みになっていた。何ともシビ
アな仕組みだった。
したという咎で、給料から一万円差し引かれる仕組みになっていた。何ともシビ
アな仕組みだった。
日曜日、心配する母親を振り切って──実際、水絵の生理痛は一日で治まる
ものだったので心配はいらなかった──水絵は授業へ出た。
ものだったので心配はいらなかった──水絵は授業へ出た。
昨日のクラスと同じクラスの授業だった。水絵は算数も教えていたのだ。倒れ
た次の日にすぐ同じクラスに出るというのは決まりの悪いことだったが、逃げる
わけにもいかなかった。
た次の日にすぐ同じクラスに出るというのは決まりの悪いことだったが、逃げる
わけにもいかなかった。
「昨日は、ごめんなさいね。もう大丈夫ですから、安心してくださいね」
小学五年の生徒たちは、最初のうちこそ少しは何となく神妙にしていたが、や
がて授業が進むにつれていつもの騒ぎぶりを発揮し始めた。
がて授業が進むにつれていつもの騒ぎぶりを発揮し始めた。
調子乗りの香山がいきなり床へ倒れこんだ。
「さ、さかぐちクーン! インターフォンを押してぇっ。センセイ、生理なのォー
ん」
ん」
水絵は頬に血がかあッと逆流するのを覚えた。香山は明らかに、昨日の自分
の真似をしている。
の真似をしている。
しかも、どこから伝わったのかは知らないが、それが生理痛だったことまで知
っているのだ!
っているのだ!
──このクラスの何人が生理だと知っているのだろう……。
考えるだけで、恥ずかしさで消え入りそうになってしまう。この年頃に生理とい
えば、どれだけ強い印象を与えることだろうか。この中の何人もの生徒が、これ
から先の一生を生理という言葉を聞くたびに祖牧水絵の名前を思い出すにちが
いない。ぞっとした。
えば、どれだけ強い印象を与えることだろうか。この中の何人もの生徒が、これ
から先の一生を生理という言葉を聞くたびに祖牧水絵の名前を思い出すにちが
いない。ぞっとした。
が、怒りが脅えに打ち克った。
水絵は、床に転がっている香山の臀部──股間に近いあたりをわざと狙った
──を靴底でぎゅうっと踏みつけて、香山の短髪を鷲づかみにし、頭皮も裂けよ
といわんばかりにか細い身体を引きずりまわした。
──を靴底でぎゅうっと踏みつけて、香山の短髪を鷲づかみにし、頭皮も裂けよ
といわんばかりにか細い身体を引きずりまわした。
「ヒィッ!」
香山は、そこまでの暴力を水絵が奮うとは思わなかったのだろう、悲鳴をあげ
て助けを求めた。
て助けを求めた。
「香山! もう一回繰り返してみろ!」
「や、やめて……」
「もう一回繰り返してみろって言ってんだよ!」
「ご、ご、ごめんなさい!」
水絵は香山を乱暴に床に放り投げた。相手が小柄な生徒だったからこそ出来
る力技だったが、かなり胸がすっきりした。そして教室は、思いがけない水絵の
反発に、皆が固唾を呑んで静まり返った。
る力技だったが、かなり胸がすっきりした。そして教室は、思いがけない水絵の
反発に、皆が固唾を呑んで静まり返った。
「い、痛いよ、痛いよぉ」
香山のすすり泣きだけが、教室に響き渡った。 その後、授業終了まで、私語
を叩くものは誰もいなかった。
を叩くものは誰もいなかった。
水絵は用意していた小テストを実施し、家へ持ち帰り採点した。
香山の答案には、字が汚いという理由で、(0と6と9との判別がつかないよう
ないい加減な数字を書く生徒だったのだ)ほとんど答えも見ずに、全ての問題
に必要以上に大きなバッテンをつけた。胸が少し癒されるのを感じた。
ないい加減な数字を書く生徒だったのだ)ほとんど答えも見ずに、全ての問題
に必要以上に大きなバッテンをつけた。胸が少し癒されるのを感じた。
それでもわたしの傷は一生癒えないだろう。そうも思った。
バイオリズムというものは、下がりはじめるとしばらくは下がりっぱなしになる
らしい。
らしい。
月曜を迎え、水絵は、生田教諭から色々具体的な注意を受けることになっ
た。
た。
どうやら生田教諭は、教育実習生の指導においては、一週間目は静観し、二
週間目に鍛える方針の持ち主らしかった。
週間目に鍛える方針の持ち主らしかった。
声のトーンにばらつきがある。
板書の文字が下手である。
生徒の様子に対して注意不足である。
用意したレジュメを見すぎる。
時間配分がまずい。
いっぺんにいろいろなことを指摘されて水絵は目が回りそうだったが、授業に
関することには今までの慣れもあってどんな厳しいチェックを受けても、自分なり
に消化できる自信があった。そして、何とか木曜までこなしたのだったが、木曜
の晩、生田教諭は冷たい目で水絵を呼びつけた。
関することには今までの慣れもあってどんな厳しいチェックを受けても、自分なり
に消化できる自信があった。そして、何とか木曜までこなしたのだったが、木曜
の晩、生田教諭は冷たい目で水絵を呼びつけた。
「祖牧さん、今日は尾崎くんが他教科の勉強をしていたことに最後まで気が付
きませんでしたね」
きませんでしたね」
「えっ……そうなんですか」
「いつになったら気がつくかと見ていたのですが……。もしかすると、あなた、
最初から気がついていたのに、億劫がって、知らない顔をしていたんじゃない
のかしら?」
最初から気がついていたのに、億劫がって、知らない顔をしていたんじゃない
のかしら?」
「そ、そんなことは」
「ねぇ、帆谷先生」
水絵はギクッとして振り返った。
職員室にちょうど車椅子を操作して入ってきた帆谷の姿が背後にあった。
帆谷は水絵の顔をさすがに認識したようで、どういう心理が働いたのかは知ら
ないが、頬を微かに高潮させた。
ないが、頬を微かに高潮させた。
「そ、祖牧さん。久しぶりです。ど、どうしたんですか」
生田教諭は底意地悪そうに続けた。
「祖牧さんは、帆谷先生の担当クラスの生徒だったらしいじゃありませんか。
見れば挨拶もろくにしないなんて、今時の若者とはいえ、教育者としてはねぇ。
いったいどういう了見なんでしょ。今日もうちの生徒が授業中に別の科目を自習
していたのに知らん顔ですよ。何でも無視すればいいとでも思っているんです
かね、いまどきのひとは」
見れば挨拶もろくにしないなんて、今時の若者とはいえ、教育者としてはねぇ。
いったいどういう了見なんでしょ。今日もうちの生徒が授業中に別の科目を自習
していたのに知らん顔ですよ。何でも無視すればいいとでも思っているんです
かね、いまどきのひとは」
水絵は顔が真っ赤になった。
生田教諭に、ここまで言われる理由が分からなかった。自分なりに一生懸命
やってきたつもりだった。
やってきたつもりだった。
が、次の帆谷の言葉は更に水絵を瞠目させるものだった。
「……いや、べ、別に、そ、祖牧さんは何も無視はしてないですよ。そういう人
じゃないです、だ、大丈夫です。ぼ、ぼ、ぼくの教え子でしたから」
じゃないです、だ、大丈夫です。ぼ、ぼ、ぼくの教え子でしたから」
「……」
──ぼくの教え子。
この人はどこから、どうやって、そんな言葉をしぼり出すことが出来るのだろ
う?
う?
「……まぁ、そうですねぇ、かつての教え子と教師の間柄ですから、わたしに
は分からない彼女の長所も帆谷先生にはお分かりなんでしょうね」
は分からない彼女の長所も帆谷先生にはお分かりなんでしょうね」
「そ、そうですね」
水絵は肩で大きく息をついた。そうでもしていないと、また貧血を起こしてしま
いそうだった。
いそうだった。
「帆谷先生の教え子、ということで、今日はもう勘弁してあげることにしましょ
う。明日一日、頑張りなさいよ」
う。明日一日、頑張りなさいよ」
そう言い残して、生田教諭は自分の席へ行ってしまった。
あとには、頬を染めた二人、水絵と帆谷が残った。
水絵は胸の前でこぶしを強く握り締めた。
「あっ、あの……」
「そ、祖牧は……」
「え」
「え、え?」
「あ、あの……」
「いや、あの」
口火を切るのに、二人の台詞が重なって散々苦しんだあと、水絵は初めて、
帆谷と会話らしい会話を交わした。
帆谷と会話らしい会話を交わした。
帆谷は言った。
「き、君たちの卒業式に出られなかったな、そういえば」
「そ、そうですね」
つられて水絵もどもった。
「先生はずっと、その、車椅子なんですか」
「ああ、これはね。骨折で筋ジスがひどくなって」
「筋ジス? 筋ジストロフィーなんですか、先生?」
「そ、そうなんだ。シャベリも下手で、き、君たちには本当に迷惑をかけて」
「いいえ、いいえ、そんな、そんな……」
水絵はこみ上げる涙を何とか飲み込んだ。そして帆谷に会釈し、実習生にあ
てがわれた準備室に逃げ込んだ。
てがわれた準備室に逃げ込んだ。
その夜は六月には珍しく、星のきれいな雲ひとつない晴れた夜だった。水絵
は自宅の三階の窓から星空を見上げた。
は自宅の三階の窓から星空を見上げた。
── 帆谷先生。筋ジストロフィー。
筋ジストロフィー。不治の病。
わたし達は何も知らずにからかった。
帆谷先生が傷ついて飛び降り自殺を図るほどに酷く、わたし達はからかっ
た。
た。
帆谷先生。ぼくの教え子、とわたしを言った。あんなに苛めたわたしを。
帆谷先生。君たちに迷惑をかけて、なんて言って、馬鹿な……。
ふと、思い当たったことがあった。
帆谷先生は、本当にわたし達を恨んでいないのだ。
間違いない、帆谷先生は、わたし達を恨むどころか、申し訳ないと本心から思
っていたのだ。
っていたのだ。
彼の憎しみは、ただただ、自分自身に向けられていっているのだ。自分の身
体の不甲斐なさ、上手くコミュニケーションを取れない不器用さ……。他人では
なく、自分だけに。不器用な考え方しか出来ない彼だからこそ、他人を憎むこと
によって器用に憎しみの対象の転換を図ることは出来なかったのだ。
体の不甲斐なさ、上手くコミュニケーションを取れない不器用さ……。他人では
なく、自分だけに。不器用な考え方しか出来ない彼だからこそ、他人を憎むこと
によって器用に憎しみの対象の転換を図ることは出来なかったのだ。
間違いない。
星空が水絵に教えてくれたような気がした。
帆谷先生はお前を憎んでいない、と。
──何て違いだろう。わたしと彼は。
水絵は思った。
わたしは、自分をからかった香山に何をしただろうか。ただ、力で押さえ込む
ことだけを考えていた。自分の憎しみだけに囚われて、生徒に復讐することし
か頭になかった。自分の立場さえ守れればそれで良かった。生徒に、わたしの
心の傷を説明する努力を怠った。たとえ分かってもらえなくても、わたしは説明
するべきだったのかもしれない。
ことだけを考えていた。自分の憎しみだけに囚われて、生徒に復讐することし
か頭になかった。自分の立場さえ守れればそれで良かった。生徒に、わたしの
心の傷を説明する努力を怠った。たとえ分かってもらえなくても、わたしは説明
するべきだったのかもしれない。
わたしは成長していない。帆谷先生が、板書する後ろから、チョークを黒板に
投げていた悪童の時代から、ちっとも。
投げていた悪童の時代から、ちっとも。
力で力を制圧することしか、わたしの教師としての姿勢は出来上がっていな
いではないか。
いではないか。
暴力では解決しない問題がある。
もし、わたしが暴行した香山──あの子が、身体の大きな高校生ならば、わ
たしは彼に暴行していただろうか?とても出来ないだろう。
たしは彼に暴行していただろうか?とても出来ないだろう。
わたしは何のために教職を目指しているのだろう……。
教師は神様じゃない。教師だって人間なんだから、傷ついたら傷ついたなりの
行動を取ればいいと思う。けれど、人間として、教育への理想を追い、子供を正
しい方向に導くアプローチをする努力はするべきではなかったか。
行動を取ればいいと思う。けれど、人間として、教育への理想を追い、子供を正
しい方向に導くアプローチをする努力はするべきではなかったか。
わたしは帆谷先生のような、聖者にはなれないけれども。
いつか水絵は泣いていた。涙は、頬をつたい、首をつたい、胸まで流れ込ん
だ。
だ。
──明日、帆谷先生ともう一度話そう。何からどうやって話したらいいか分か
らないけれど、どうやったら彼の心の傷を深めずに癒せるか分からないけれど、
とにかく明日、彼と話そう……。
らないけれど、どうやったら彼の心の傷を深めずに癒せるか分からないけれど、
とにかく明日、彼と話そう……。
翌日の金曜、水絵の教育実習は終わった。
厳しかった生田教諭は、あなた、きっといい先生になるわよ、と最後に思いが
けないはなむけの言葉をくれた。
けないはなむけの言葉をくれた。
帆谷は、たまたま会議とのことで、他校へ出張し、不在だった。
水絵は拍子抜けしたが、気持ちの高ぶった一夜が明けてみれば、いったい自
分が何を帆谷に伝えたかったのか、もうひとつ釈然としない。帆谷に会えなく
て、残念なのか、ラッキーだったのか。
分が何を帆谷に伝えたかったのか、もうひとつ釈然としない。帆谷に会えなく
て、残念なのか、ラッキーだったのか。
ともあれ、そうして、水絵の教育実習は終了した。
帆谷の死の知らせを聞いたのは、それから三年後の同窓会の席だった。
生活指導の山口教諭の酌をする羽目になった──どうやら水絵は山口教諭に
何故かしら好かれているようだった──水絵は、彼の口から帆谷教諭は半年
前に亡くなった、と聞かされた。
何故かしら好かれているようだった──水絵は、彼の口から帆谷教諭は半年
前に亡くなった、と聞かされた。
「半年前、ですか」
「ああ、人間の命なんてはかないもんやわ。でもあの人はちがったで。祖牧は
知っとるかどうかしらんが、筋ジスいう病気は進行していくんや。新任の頃は、
兆候はあっても分からんかったんやな。あの不自然な動作は、本人も周囲も仕
草の癖やと思いこんどった。いつ頃本人が筋ジスにかかっとるのに気づいたん
かは知らんが、あの転落事件は、ひょっとするとそれを気に病んでのもんやっ
たかもしれへんなぁ。今となっては分からんことやが……最後は、ほとんど動け
へんようになって、それでも亡くなる三週間前まで通勤してきはった……執念の
固まりやったんや」
知っとるかどうかしらんが、筋ジスいう病気は進行していくんや。新任の頃は、
兆候はあっても分からんかったんやな。あの不自然な動作は、本人も周囲も仕
草の癖やと思いこんどった。いつ頃本人が筋ジスにかかっとるのに気づいたん
かは知らんが、あの転落事件は、ひょっとするとそれを気に病んでのもんやっ
たかもしれへんなぁ。今となっては分からんことやが……最後は、ほとんど動け
へんようになって、それでも亡くなる三週間前まで通勤してきはった……執念の
固まりやったんや」
「そうですか……」
水絵は山口教諭のグラスにビールを注いだ。山口教諭がビールを注いでくれ
たグラスに唇をつけて、そっとひと口呑んだ。
たグラスに唇をつけて、そっとひと口呑んだ。
「ね、先生、覚えてはりますか」
「え?」
「山口先生は、帆谷先生がベランダから落ちて骨折した時、わたしらのクラス
に知らせに来はったんです。そのときにおっしゃった言葉」
に知らせに来はったんです。そのときにおっしゃった言葉」
「え。おれ、何か言うたかな」
「わたし達、笑ったんです。帆谷先生が怪我をしたのが可笑しいって。そした
ら山口先生、『お前らには人の心があらへんのか。覚えとけ、今笑ったヤツは
一生後悔すんぞ』って、たしかそう、おっしゃったんです」
ら山口先生、『お前らには人の心があらへんのか。覚えとけ、今笑ったヤツは
一生後悔すんぞ』って、たしかそう、おっしゃったんです」
「……そんなことも、あったかなぁ。まあ、いろいろ、苦労の多い人やったから
な」
な」
「山口先生は正しいことをおっしゃったんですよ、あのとき、たぶん。今笑った
ヤツは、……今笑ったヤツは一生後悔するって」
ヤツは、……今笑ったヤツは一生後悔するって」
「おいおい、それはその時の話や。みんな子供やったんや、おまえも。そんな
に気にせんでもええ、しゃあないんや」
に気にせんでもええ、しゃあないんや」
「でもわたし、今分かったんです。わたし、帆谷先生に再会したときに、言わな
あかんかった。帆谷先生は、自分を憎んじゃいけなかったんですよ。帆谷先生
は、他人を憎むことも覚えるべきだったんです。それを言ってあげられなかった
のが、わたし、悔しくて」
あかんかった。帆谷先生は、自分を憎んじゃいけなかったんですよ。帆谷先生
は、他人を憎むことも覚えるべきだったんです。それを言ってあげられなかった
のが、わたし、悔しくて」
「……そうやなあ。そうかもしれへんなあ。他人を憎むことを覚えるべき、か。
でも、それを覚えると、あの人のええとこがひとつ減ったかもしれへんなぁ」
でも、それを覚えると、あの人のええとこがひとつ減ったかもしれへんなぁ」
それは、そうかもしれなかった。
水絵はビールを飲み干した。山口教諭がビールを継ぎ足してくれた。水絵はも
う一度ビールを半分飲み干した。溢れる涙をビールの流れとともに飲み干せる
ものなら。そう思い、水絵は苦いビールを飲み続けた。
う一度ビールを半分飲み干した。溢れる涙をビールの流れとともに飲み干せる
ものなら。そう思い、水絵は苦いビールを飲み続けた。
ああ。苦い。生きることは、こんなにも、苦い。生きることは、こんなにも切な
い。なのに寡黙で温かい人の心は、死んでなお、こんなにも生きていることの素
晴らしさを教えてくれる。
い。なのに寡黙で温かい人の心は、死んでなお、こんなにも生きていることの素
晴らしさを教えてくれる。
水絵は思った。
わたしの中で答えはまだ出ない。
わたしはどうするべきだったのだろう。
たとえば、帆谷先生が、病気ではない、ただの不器用な話下手の教師だった
としたら?
としたら?
わたしは彼を許し同情しただろうか?──とてもそこまでわたしの心は広くな
い。
い。
たとえば、わたしが在職中に、事故か病気によって、授業に支障の出るような
身体になり、それを生徒に嫌悪されたとしたら?
身体になり、それを生徒に嫌悪されたとしたら?
自分だったらきっと何か手を打つだろう、と思う。
自分の身体について、人間の障害というものは誰もがいつでもなり得るものな
のだ、と説教のひとつもうつだろう。勝気なわたしの性格であれば。
のだ、と説教のひとつもうつだろう。勝気なわたしの性格であれば。
もしも自分がもう一度生理痛で倒れ、それを生徒にからかわれたとしたら?
わたしは、にくしみを交えずに相手を諭すことが出来るだろうか。ああ、とて
も、無理だ。
も、無理だ。
人間とは理屈では動かない感情の動物だもの。その現実を生徒にも分かって
欲しいと思うだろう。
欲しいと思うだろう。
何の言い訳もせず、ただ自分だけを責めた、帆谷先生のようには、とても振舞
えない。
えない。
帆谷先生は、馬鹿だったのだろうか。
それとも、聖人だったのだろうか。
きっとどちらでもないのだろうと思う。ただ、彼はそういう性格の人だったの
だ。
だ。
ああ。
あの時笑ったことを、あの時意地悪したことを、そして最後に出逢ったときせ
めてお詫びのひとことも言えなかった卑しい自分を、わたしは思い出すたびに
一生後悔するのだろう。山口教諭のあの言葉は、本当に正しかった……。
めてお詫びのひとことも言えなかった卑しい自分を、わたしは思い出すたびに
一生後悔するのだろう。山口教諭のあの言葉は、本当に正しかった……。
帆谷先生は二回空を飛んだのだ。と水絵は思った。
一度目は、たぶんみずから身体を叩きつけるために。
先生は飛び立つことは出来ず、地へ落ち、身体に障害を残した。
そしてもう一度、先生は自らの意志ではなく、空を飛んだ。
皮肉にも今度は飛び立つことに成功したのだ。
先生はもう地上に戻ってくることはなかった。
天使が、彼の純情な魂を天へさらってしまったのだから。
<おわり>
(2002.2.8 初稿)
(2002・7・6 改稿・挿絵挿入)