彩木 映
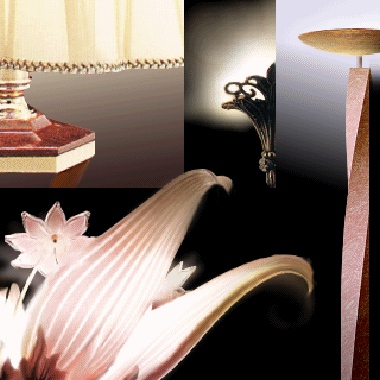
2002年2月13日、萩原晃(はぎわら あきら)と木村夏海(きむら なつみ)は
宝塚市役所に婚姻届を提出した。
宝塚市役所に婚姻届を提出した。
萩原晃は、木村晃になった。
二人で話し合った結果、妻となる夏海の姓を使うことにしたのだ。
晃にとって、その方がなにかと都合が良かった。
第一に、晃はシンナー吸引と窃盗、恐喝などで何度も補導された前科があっ
た。苗字を変えることで、そんな経歴から心機一転できるような予感がした。
た。苗字を変えることで、そんな経歴から心機一転できるような予感がした。
第二に、萩原という姓は、晃と血のつながっていない男の名前だった。しかもそ
の萩原洋司(はぎわら ひろし)は死んでこの世にはもういなかった。そんな若
死にするようなツキのない男の姓を、たまたま母の最後の夫だからといってい
つまでも名乗っているのは、晃にしてみれば「ケッタクソが悪い」ことだった。
の萩原洋司(はぎわら ひろし)は死んでこの世にはもういなかった。そんな若
死にするようなツキのない男の姓を、たまたま母の最後の夫だからといってい
つまでも名乗っているのは、晃にしてみれば「ケッタクソが悪い」ことだった。
ただ、公平にいうならば、晃は萩原洋司に大きな恩恵を受けていた。いや、今も
まだ受けている。高校を卒業する三月までは、晃は萩原洋司の遺族年金を受
けられるのだった。
まだ受けている。高校を卒業する三月までは、晃は萩原洋司の遺族年金を受
けられるのだった。
しかし、結婚したことによって、晃には遺族年金があたらなくなる。
晃の高校卒業まで婚姻届を出すのを待ってもよかったのだが、ある想いがあっ
て晃はあえて婚姻届を二月に提出した。
て晃はあえて婚姻届を二月に提出した。
もう、遺族年金はいらない、と晃は思ったのだ。
母が受給している遺族厚生年金は減額されるが、減額されても同じだった。
生活保護費が増えるだけだ、おそらく。
そして、もし、生活保護費の増額申請が認められなくてもかまわないと晃は思っ
ていた。
ていた。
結局、香澄の今の男──晃が世界で一番憎んでいる男、高城宗生(たかぎ
むねお)のふところに転がりこむ小遣いが減るだけの話なのだから。
むねお)のふところに転がりこむ小遣いが減るだけの話なのだから。
晃の若い母、三十四歳の萩原香澄(はぎわら かすみ)は、その遺族年金と、
市役所で受ける生活保護費で暮らしていた。
市役所で受ける生活保護費で暮らしていた。
萩原洋司が亡くなったのは、今から五年前のことである。
萩原が死んで一年もしないうちに、香澄には新しい男が出来た。
それが晃がすさんだ原因を作った男、高城宗生だ。
晃は高城宗生を憎んでいた。
香澄は、晃から見ればアタマが軽いだけが取り得の、どうしようもない女だっ
た。
た。
けれどもどういうわけか、香澄には、いつでも、どんな時でも、男が絶えることが
ないのだった。
ないのだった。
晃が生まれる前の香澄の男遍歴までは知らない。
が、晃が生まれてからはほとんど香澄は男を切らしたことがない。
香澄の男遍歴はざっとこんなものだ──まず、晃の父親。杉本毅(すぎもと つ
よし)という名の男で、香澄よりも二十才も年齢が上だったという。
よし)という名の男で、香澄よりも二十才も年齢が上だったという。
香澄は十六歳で晃を生み、しばらく杉本と暮らした。
そして理由は晃には分からないが、晃が四歳のとき、つまり香澄が二十歳のと
きに杉本と香澄は離婚した。
きに杉本と香澄は離婚した。
そして一年後、香澄は自分より十歳上の萩原洋司と結婚した。
萩原とは八年間、萩原が亡くなるまで連れ添った。
今の男、高城宗生は、その萩原が死んでから香澄にヒモのようにまとわりつい
て、もう五年近くになる。
て、もう五年近くになる。
高城宗生。晃の立場から端的にいうなら、『ろくでもないヤロー』だった。
萩原──つまり自分のオンナの前夫(!)──の遺族年金を受け取るために、
香澄とずっと一緒にいるにもかかわらず入籍をしていない。
香澄とずっと一緒にいるにもかかわらず入籍をしていない。
なぜなら、香澄が高城と入籍したら、再婚となる。新しい夫が出来た女性には、
当然のことながら前夫の遺族年金は支給はされない(失権となる)法律になっ
ているからだ。
当然のことながら前夫の遺族年金は支給はされない(失権となる)法律になっ
ているからだ。
遺族年金の受給という事情に阻まれて再婚出来ない寡婦は多いと、以前、不
良仲間の先輩に聞いたことがある。
良仲間の先輩に聞いたことがある。
香澄と高城が入籍しないのは、つまりだから、そういうわけだ。
で、高城は香澄の遺族年金を掠め取る。
それを考えると晃は怖気がたつ。いじましい男。いやらしい下司野郎。
「このデザイン、どうかなぁ」
うわの空だった晃の目の前に、銀色に光るものが差し出された。
「ええ、そちらのデザインは今カップルの方にとても人気なんですよ。当店でもい
ちばんよく出ている売れ筋でございますよ」
ちばんよく出ている売れ筋でございますよ」
唇をぬらぬら光るグロッシーなサーモン・ピンクに染めあげた店員が、晃に愛想
の良いつくり笑顔を見せた。
の良いつくり笑顔を見せた。
夏海はつないだ手を離し、晃の左手をガラスのショーケースの上にむりやり引き
ずりあげた。
ずりあげた。
「ほら、はめてみて。どう? 似合ってるやん」
「あ、ああ。別にいいけど…」
二人は左薬指のサイズを綿密に測ってもらい──晃にとっては、自分の指を測
るというのははじめての経験だった、オンナが指を測るのを横で見ていたことは
あっても──店員いわく一番人気との、そのシルバーのペアリングを購入する
ことに決めた。
るというのははじめての経験だった、オンナが指を測るのを横で見ていたことは
あっても──店員いわく一番人気との、そのシルバーのペアリングを購入する
ことに決めた。
晃が財布から金を出そうとすると、夏海がおしとどめた。
「いいよ、あたし払うから。バレンタインだもん」
「なんでや」
晃は反論した。
「あかん、あかん。こんなんは、バレンタインとは別モンや。これは結婚指輪な
んやからな」
んやからな」
「晃、声が……」
「え」
周囲の視線を感じた。
ケッコンユビワ。
目立つ単語を傍若無人に叫んでしまった。
晃は頬が赤くなるのを感じた。
「──とにかく、こんなんは互いの分を互いに買って贈り合うもんや。そうやろ」
店員は気を回し、慶事仕様のコトブキ印の包装紙で、シルバー・リングを包んで
くれた。
くれた。
考えてみればその店員は、心の温かい女、もしくは店の教育のゆきとどいた女
だったのかもしれなかった。
だったのかもしれなかった。
結婚指輪と聞いて、高価なプラチナリングをあえて薦めてこなかったのは、晃に
とっては有難かった。内心、それを少し恐れていたのだ。
とっては有難かった。内心、それを少し恐れていたのだ。
晃と夏海に、プラチナを買うだけの金はなかった。結婚式をあげる金もなかっ
た。ささやかな祝いの飲み会を企画してやるよ、と言ってくれた友人たちはいた
けれども。
た。ささやかな祝いの飲み会を企画してやるよ、と言ってくれた友人たちはいた
けれども。
宝石売り場の店員は、親切心からではなく、晃と夏海のみすぼらしい服装を見
て、プラチナを薦める徒労を敢えて冒さなかったのかもしれない。
て、プラチナを薦める徒労を敢えて冒さなかったのかもしれない。
二月の寒い公園が、二人の結婚式場になった。
ひと気のない公園では、ブランコが風に揺られて、錆びた鎖がきい、きいと寂し
い音をたてていた。曇天だった。ねずみ色の雲は近くの高層マンションの上階
にひっかかりそうなほどに低かった。
い音をたてていた。曇天だった。ねずみ色の雲は近くの高層マンションの上階
にひっかかりそうなほどに低かった。
たそがれ時のせまる昼下がり。茜色と黄金色を混ぜた陽光が、ねずみ色の雲
と雲のあいだのわずかな隙き間を照らす。
と雲のあいだのわずかな隙き間を照らす。
コトブキ模様の包装紙を破いて、指輪を取り出し、包装紙と箱を公園のゴミ箱に
捨てた。
捨てた。
雨ざらしの腐りかけた木製のベンチにふたりは腰掛けた。
晃と夏海は、そっと互いの指に指輪をはめた。
指輪はぴったりとはまった。
そしてふたりは凍えた唇をいたわりあうようにそっとあわせた。
唇をはなして、晃はこれから先、妻として連れ添っていくことを決めた女の顔をじ
っと見つめた。
っと見つめた。
二十才の夏海。
赤いマフラー。小柄な身体に、赤はよく似合っている。
赤茶色に染めた髪。
リンゴ色に染まった頬、まるいやさしい曲線を描いて、寒い空気の温度をほん
のりと上げるような頬。
のりと上げるような頬。
口紅ははげているけれど、その生身のうすい唇がなまめかしいと晃は思った。
マスカラで流行のかたちにボリュームアップされた睫毛、だけどそんな飾りがな
くても夏海の瞳はくりっと大きくまっすぐに澄んでいる。澄んで晃の姿を映してい
る。
マスカラで流行のかたちにボリュームアップされた睫毛、だけどそんな飾りがな
くても夏海の瞳はくりっと大きくまっすぐに澄んでいる。澄んで晃の姿を映してい
る。
自分は夏海の瞳にどんな姿を晒しているだろうか。晃はあまり考えたくないこと
を考えた。
を考えた。
十八歳の自分。
一人前に身体だけは大きく、にきびの跡がひどい、一重まぶたの人相の悪いツ
ラ。根元が黒くなった金髪。
ラ。根元が黒くなった金髪。
「愛してる、晃。──ねぇ、愛してる?」
「愛してるさ……」
どれほどおれが夏海を愛しているか、夏海には分かるまいと晃は思う。
自分は感情を表現することが上手くない。
いや、場合によっては激烈な感情を披露することも出来るのだ、ただ、そういう
芸当は喧嘩の場面でしか出来やしない。
芸当は喧嘩の場面でしか出来やしない。
こういう甘い場面は苦手だ。柄じゃない、でも、夏海を全身全霊をかけて愛して
いる。愛している。誰よりも何よりも愛している、愛している──
いる。愛している。誰よりも何よりも愛している、愛している──
高城宗生が母にしているような想いはさせない、おれの魂をかけて!
孤独だった晃の魂の、すべての拠りどころが彼女の小さな肢体のうえにあっ
た。
た。
「おれは木村夏海を一生愛します。…何て言うんやっけな。よくあるやん、えっ
と」
と」
「あのね、たしかね、……あたしは萩原晃を富めるときも貧しいときも健やかな
るときも病めるときも愛します」
るときも病めるときも愛します」
「そうか、そんなんやったな。ええと、おれは木村夏海を富めるときも貧しいとき
も、……健康なときも病気のときもブサイクになってもオバンになってもいつもい
つも愛し続けます」
も、……健康なときも病気のときもブサイクになってもオバンになってもいつもい
つも愛し続けます」
「アドリブやわぁー」
「ハハ…」
「ね、寒くない? 買い物して帰ろ。香澄サン待ってはるよ。チョコレートケーキを
作るって約束してんねん」
作るって約束してんねん」
「あー、そうやったな」
甘い思いは立ち消え、現実が晃のもとへ帰って来た。家には香澄がたぶん一
人で待っている。
人で待っている。
ハート型のケーキ型と、その他もろもろの道具を揃えて、二人が帰ってくるのを
待っているはずだ。そしてたぶん、高城はいない。
待っているはずだ。そしてたぶん、高城はいない。
ふと晃は胸が煮えくり返るのを感じた。そうだ、高城はいない。
どうせいつものオンナに会いに行っているんだろう。あの野郎、よそのオンナ
に、お袋を置いて、お袋の金で……!
に、お袋を置いて、お袋の金で……!
築三十数年、貧乏という言葉を体現するに最適ではないかと晃がしばしば思
う、古くてボロ臭い文化アパート。
う、古くてボロ臭い文化アパート。
二階の東向きの2DKの部屋が、晃と香澄と夏海と宗生が暮らす部屋だった。
もっとも、宗生は留守にしていることがほとんどだったが。
もっとも、宗生は留守にしていることがほとんどだったが。
「おっ帰りぃー」
香澄の、脳天から出しているようなピィピィ声がふたりを迎えた。
香澄は黄色のエプロンをセーターの上から身につけて、チョコレートケーキ作り
に準備万端の態勢でふたりの帰りを待っていたのだ。
に準備万端の態勢でふたりの帰りを待っていたのだ。
「遅くなっちゃって」
夏海が申し訳なさそうにブーツを急いで脱ぎ捨てながら謝った。
「指輪を見ていたものですから…」
「そりゃもう、全然かまわへんわよぉ。おめでたいことやもの。婚姻届は無事受
け付けてもらえたのね? 良かったねー、指輪はどんなん買ったん?」
け付けてもらえたのね? 良かったねー、指輪はどんなん買ったん?」
「ホラ、これや」
ブーツと悪戦苦闘している夏海を救うために、晃は香澄に指輪を抜いて差し出
した。
した。
「へぇッ! ほぉー。え、うわ、何これ、ゆがんでない?」
「そういうデザインなんだよっ」
「楕円やね。しゃれてるねー、ボーイッシュでさ。でも、夏海ちゃんは、こんな男っ
ぽいので良かったん?」
ぽいので良かったん?」
「あたしが選んだんですよ、それ」
夏海はようやく脱いだブーツを揃え、荷物をリビングへ置いた。
「こういうデザインだと、晃クンの指に似合うかなぁ、って。シャープで、イイと思っ
たんです」
たんです」
基本的に育ちの良い夏海は、母親の前では晃のことを決して呼び捨てにはしな
い。
い。
最初は『晃サン』と呼んでいたものだったが、最近少し慣れてきて『晃クン』にく
だけた。
だけた。
それにしても晃はすこし驚いた。
指輪を、夏海がそんな基準で選んでいたなんて。
自分は宝石売り場に行くときの癖で、上の空になっていた。何も考えず指輪選
びに『付き合っていた』ような自分が、恥ずかしくなった。
びに『付き合っていた』ような自分が、恥ずかしくなった。
母に返してもらったシルバーリングをあらためて見つめる。
たしかに、指輪は男性的なフォルムを描いて、シャープにゆがんだデザインで、
晃の指にしっくり似合っていた。
晃の指にしっくり似合っていた。
晃はこっそりと夏海の指を見つめる。
彼女に似合うかどうかなんて、おれは考えもしなかった……。
「そっかぁ。ええ嫁さんやでー、アンタは」
「へへへー」
「さ、作ろう作ろうー。アタシ、チョコレートケーキを焼くのは初めてやねん。頼り
にしてんで、夏海ちゃん」
にしてんで、夏海ちゃん」
「あ、ハイ、やりましょう」
二人が台所でバレンタイン向けのささやかなケーキを作りはじめるのをよそに、
晃はダイニングの椅子に座り、テレビのチャンネルをひねった。
晃はダイニングの椅子に座り、テレビのチャンネルをひねった。
萩原家のテレビは未だに円形のチャンネルをカチャカチャ回す、骨董品的な代
物である。リモコンなどついている訳もなかった。
物である。リモコンなどついている訳もなかった。
「あれ? これ、どないしたん? 高城サンのヤツか?」
高城に敬称などつけたくはなかったが、一緒に暮らしている以上、適当な距離
を取るための選択をせざるを得ない。
を取るための選択をせざるを得ない。
無論、母と結婚しない高城に「お父さん」と呼ぶ義理はさらさらないぞ、というの
が晃の言い分で、「高城サン」という呼び方は、晃が母と歩み寄った結果の妥
協の産物だった。
が晃の言い分で、「高城サン」という呼び方は、晃が母と歩み寄った結果の妥
協の産物だった。
晃はテーブルの上に置いてあった、黒と赤と金の豪華な包装紙で包んである箱
を指差した。
を指差した。
「なぁ、お母んって! 何や、これ?」
「え、何? ああ、それ」
母が銀のボールの中身を何やら泡立てながら、台所から出てきた。
「それ、そうそう! 開けていいで、晃。宗生ちゃんが食べていいって。義理チョ
コもらってんて。でもあのヒト、甘いモンたくさんは食べられへんからって置いて
ってん」
コもらってんて。でもあのヒト、甘いモンたくさんは食べられへんからって置いて
ってん」
「へえ……」
「夏海ちゃん! アンタ、甘いの好きやろ? ちょっと休もう。夏海ちゃん、来て。
食べなさいよ」
食べなさいよ」
「ハイー?」
夏海は呼ばれて、エプロンの裾で指をぬぐいながら来た。
晃はさっそく、バリバリと包装詩をはがしはじめた。
甘いものは好きなのだ。
「夏海ちゃん、これねぇ、義理チョコだって宗生ちゃんが。でもこんなたくさんは食
べられないんやって。食べなさいよ」
べられないんやって。食べなさいよ」
「おお、食えよ夏海。うまいでこれ、上等なんとちがうかな」
むしゃむしゃと晃はチョコを頬張りながら、夏海にひとつ銀紙を向いて差し出し
た。
た。
ふいに、MISIAの『果てなく続くストーリー』の電子音が響き渡った。
「あ」
三人は顔を見合わせた。それは、高城宗生の携帯の着信音だった。
「あら、宗生ちゃん、携帯忘れて行ったんかしら」
香澄が自分と高城の寝室に使っている部屋に走り、携帯を手に戻ってきた。
「あらー、忘れてったんやわ。宗生ちゃん。電話、出たいけど、あかんやろな」
「そらあかんやろ。また喧嘩になんで」
香澄の前歯は二本が半分欠けていた。宗生に殴られた跡だった。
その前歯の欠落は、香澄の生まれながらに持つ清楚な美しさを相当にそこなう
ものだった。
ものだった。
が、保険のきかない高価なセラミックで歯の治療をする金など、萩原家にはあり
はしなかった。
はしなかった。
「誰からや。何これ、Rとしか表示されてへんなぁ。怪しいヤツ」
「やめとこうよ、ヒトの携帯見るの。自分だってそんなんされたらイヤやん、晃ク
ン」
ン」
夏海が眉をしかめながら言った。
それはまあ、そうだ。晃は宗生の携帯をテーブルの上に放り出した。
夏海は晃からもらったチョコを食べずに、親指と人差し指で、汚いものでもつま
むように持ってたたずんでいた。
むように持ってたたずんでいた。
「…あの」
「え?」
「あの……あの、ですね。……」
「どうしたん、夏海ちゃん」
「これ、義理チョコなんでしょうか。買ったら高いですこれ。ブランドものですよ。こ
んな量なら、四千円くらいすると思うんです」
んな量なら、四千円くらいすると思うんです」
「え…」
口の中のチョコを急に吐き出したくなった。
晃はテーブルの上の豪華なチョコレートの詰め合わせを凝視した。
「ブランドもの……」
放り出した携帯をもう一度取り上げる。
今更、腹を立てることでもないはずだった。
分かってはいたのだ。分かってはいるのだった、が。
晃は神経質に携帯のボタンをカチカチと操作し、着信履歴を開いていった。
「……ホンマやわ。おふくろ、見てみいや。R、R、Rって…Rって誰やねん」
「ええやん、別に」
香澄は割れた歯を剥き出して、にっこり微笑んだ。
こういう、くもりのない笑顔を見せるとき、晃は自分の母親はちょっとアタマが足
りないんじゃないかと思う。
りないんじゃないかと思う。
一方で、おれの母親は心底強い女なんだ、とも思う。
「誰からもらったものでもね。モノに罪はないのよ。ええやん、食べよ食べよ。気
にすることあれへんよ」
にすることあれへんよ」
香澄はことさら気にしていない様子を顕示するように、チョコレートを頬張って見
せた。
せた。
「何で食うねん! 食うなや、こんなん、口が腐る! 捨てよ捨てよ! 捨てる
で!」
で!」
額の中で光がはじけるような気がした。
はじけた閃光は晃の眼底を、鼻腔を、喉元を走り指先まで突き抜けた。
晃は流れる涙を隠そうともせずに、チョコレートの箱をひったくって、ゴミ箱の中
に押し込んだ。箱はゴミ箱に収まるには大きすぎた。
に押し込んだ。箱はゴミ箱に収まるには大きすぎた。
溢れる感情の波の勢いにまかせて、晃はめちゃくちゃに箱を折り曲げようとし
た。が、紙の厚みによって箱がうまく曲がらなかった。晃は箱を床に叩きつけ
た。チョコレートが飛び散った。
た。が、紙の厚みによって箱がうまく曲がらなかった。晃は箱を床に叩きつけ
た。チョコレートが飛び散った。
「晃!」
「やめなさい、晃。こら、やめなさいったら!」
「何でや、こんなん、こんなん、何で食ってん! くそぉっ!」
「もう、晃は……」
一瞬の激情が去ると、あとには感傷を抑えることが出来ない自分のことを、惨
めに感じる自嘲しか残らなかった。
めに感じる自嘲しか残らなかった。
夏海が黙って、飛び散ったチョコレートや引きちぎられた箱の切れ端を集めはじ
めた。
めた。
晃は涙で濡れた顔をフリースの袖で拭った。
「夏海ちゃん、チョコレートは置いておきなさい。捨てたらあかんで。生活保護で
生活してるアタシやもん、食べ物を粗末にしたらバチが当たるわ。モノに罪はな
いんやで。アタシは、別れた男にもろたモノも、捨てへん主義やもん」
生活してるアタシやもん、食べ物を粗末にしたらバチが当たるわ。モノに罪はな
いんやで。アタシは、別れた男にもろたモノも、捨てへん主義やもん」
「それは何度も聞いとるわ」
晃は毒づいた。
が、彼はおとなしくチョコレートを集めて、テーブルの上に戻すのを手伝った。
「あ」
香澄が生来の高い声を更に高く上げて叫んだ。
「しもた! スーパーが閉まるわ!仕上げの粉砂糖買いに行かんと忘れてたね
って、さっき夏海ちゃんと言ってたんよ。アタシ、ちょっと行ってくるわ」
って、さっき夏海ちゃんと言ってたんよ。アタシ、ちょっと行ってくるわ」
「あ、あたし行きますよ」
「ええねん。アタシ行ってくる、車に乗らないとあかんし。アタマ冷やしてくるわ」
「あ、お母さん……」
大抵はおっとりとした香澄だ。が、ときどきすばやい動作を見せて周囲の人間を
かわすことがある。今がそうだった。
かわすことがある。今がそうだった。
香澄は一瞬でコートをひっかけ、セカンドバッグをつかみ、パンプスを履いてドア
の外にバタンと出て行った。
の外にバタンと出て行った。
あとには、呆然とした晃と夏海が残された。
「……あたし、作るね、ケーキ」
「あ、ああ」
ケーキ。チョコレートケーキ。
チョコレートケーキを作りたいと言い出したのは香澄だった。
夏海と晃の結婚祝いも兼ねて。
『家族みんなで』バレンタインを迎えるためのチョコレートケーキ。
家族みんなでって何だ。どんな家族だ。
萩原香澄、高城宗生、木村晃、木村夏海。苗字が三つもある。そんな家族。
どんな顔だか知らないが、ともかく恋人であることは間違いないだろう『R』という
オンナのもとへ通う高城宗生。
オンナのもとへ通う高城宗生。
そんなヤツのためにチョコレートケーキを作る萩原香澄。
そんなの変だよ。ダミーだよ。フェイクだよ。
おれと夏海の結婚指輪がすぐに錆びてしまうシルバーだってのと同じくらい。
いや、もっと奇妙だ。奇態だ。何がチョコレートケーキだ。何がモノに罪はナイ
だ。嘘ばっかりの人生だ。
だ。嘘ばっかりの人生だ。
香澄の人生は欺瞞で塗り固められている、嘘ばっかりだ、いつも、いつも、いつ
も!
も!
入籍の問題だってそうだ、カネの問題だってそうだ、気の良さそうな顔をしてア
イツは、香澄は社会に寄生して暮らしている!
イツは、香澄は社会に寄生して暮らしている!
遺族年金も生活保護も要は国のカネだ、他人のカネだ!
そしてその香澄に養われているおれは。おれは香澄以下だ。
役所関係の手続きをするのはいつも香澄だ。おれは泥を香澄ひとりにかぶせて
被害者みたいな顔をして香澄に寄生しているんだ。
被害者みたいな顔をして香澄に寄生しているんだ。
夏海は台所へ引っ込み、『チョコレートケーキ』を作っている。何のためにそんな
ものを作っているんだろう。何のために。誰のために。
ものを作っているんだろう。何のために。誰のために。
晃はテレビの画面を気抜けした顔で見つめた。
ちょうどソルトレーク冬季五輪の時期で、テレビ画面ではスピードスケートの実
況中継をやっていた。
況中継をやっていた。
しかし、アナウンサーの白熱した声も、晃の褪めきった頭にはただひたすらに
虚しく響いた。
虚しく響いた。
晃は舌打ちをした。
触るのも汚らわしかったが、高城宗生の携帯電話をもう一度取り上げた。メー
ルの履歴は簡単に開いた。
ルの履歴は簡単に開いた。
「十四日、都合が悪くなってごめんね。十三日、十九時『囲炉裏』に予約を取り
ました。地酒と鯨が美味しいので有名なお店なんです。楽しみにしてるね。梨
花」
ました。地酒と鯨が美味しいので有名なお店なんです。楽しみにしてるね。梨
花」
梨花。RIKA。R。
晃は次々にメールを開いていった。
「ゆうべはご馳走になりました。おいしかった。いいお店を教えてくれてありがと
う、友達にも教えます。梨花」
う、友達にも教えます。梨花」
「ハリー・ポッターを観たいなんて意外(笑)子供も大人も楽しめる夢のあるスト
ーリーだと聞いてます。だけど、流行りものってハズレはあるよ。バトル・ロワイ
アルは怖いだけだったもんね。三十日はあいてる? 梨花」
ーリーだと聞いてます。だけど、流行りものってハズレはあるよ。バトル・ロワイ
アルは怖いだけだったもんね。三十日はあいてる? 梨花」
「今日もパチンコやってるんかなぁー。当たったらご馳走してね。でもほどほどに
した方がいいよ。……」
した方がいいよ。……」
晃は鼻息を吹いて携帯を放り投げた。
ラベンダーシルバーの携帯は、カーペットの上でポーンとはずんでテレビの横に
転がった。
転がった。
──何なんだ、あいつ。子供みたいな恋愛しやがって。
ふと、思い当たった言葉があった。
援助交際。これは援助交際なのかもしれない。
梨花は何歳なんだろうか?
高城宗生は四十才だ。
仕事はフリーター、少なくともこの五年間ヤツはずっとフリーターだった。
甘いマスクのハンサムだが、柄の悪い男で、前科は六犯。
ヤツの教育で、おれは恐喝や万引きのテクニックを教わった。夏海に出遭わな
ければ、今もおれは高城の子分気取りで、毎日を悪事に費やしていたにちがい
ない。
ければ、今もおれは高城の子分気取りで、毎日を悪事に費やしていたにちがい
ない。
「ねぇ、お母さん、遅くない? もう十時なんだけど。ケーキも焼けちゃったよ」
「あ。……ホンマや」
時計を見た。香澄が逃げるように部屋を飛び出た理由が、『スーパーが閉ま
る』。
る』。
そしてスーパーといえば、香澄はいつも生協に行く。
生協は八時に閉店するから、香澄は少なくとも八時より前に家を出てから帰っ
てこないのだ。たかだか粉砂糖を一箱買うだけのために。
てこないのだ。たかだか粉砂糖を一箱買うだけのために。
背筋がぞくりとした。
一晩中待ったが、翌日の二月十四日に日付が変わっても香澄は帰って来なか
った。警察に通報しようかとも思ったが、香澄は以前から時折こういうことがあ
ったため、下手に動くこともためらわれた。
った。警察に通報しようかとも思ったが、香澄は以前から時折こういうことがあ
ったため、下手に動くこともためらわれた。
彼女は家でトラブルがあると、知人、友人宅に転がりこむ癖があるのだ。親や
兄弟の家には決して行かないくせに。
兄弟の家には決して行かないくせに。
午前九時すぎ、電話が鳴った。まんじりともしていなかった晃と夏海は飛び上
がった。あらゆる悪い妄想を思い浮かべながら、晃は肩をこわばらせて受話器
を取り上げた。
がった。あらゆる悪い妄想を思い浮かべながら、晃は肩をこわばらせて受話器
を取り上げた。
「もしもし?」
「もしもし、萩原さんのお宅ですか? こちら病院なんですけど、息子さん? お
母さんが事故に遭われて、私どものK病院に運ばれたんですよ。命に別状あり
ませんが、肋骨を骨折されてるんで、入院の手続きが必要です。ちょっと来ても
らえませんかね。必要なものは……」
母さんが事故に遭われて、私どものK病院に運ばれたんですよ。命に別状あり
ませんが、肋骨を骨折されてるんで、入院の手続きが必要です。ちょっと来ても
らえませんかね。必要なものは……」
「え! ……はい。はい、はい……」
電話機の横に置かれたメモ用紙にペンを走らせながら、晃は奇妙な安堵感を
覚えていた。
覚えていた。
最悪の予感は外れた。
香澄は生きている。
肋骨骨折。重傷だが、普通、命にかかわるものではないだろう。
「母はどこで事故ったんでしょうか」
質問すると、電話の相手の女性はそこまで知らなかったのだろう。
何やら受話器の向こうで会話をしている声が聞こえてきた。五分ほども待たされ
て、ようやく返事がかえって来た。
て、ようやく返事がかえって来た。
「武庫大橋はご存知ですかね? あそこのガードレールに衝突されたそうです
よ」
よ」
「そうですか……」
「じゃ、お待ちしていますからね。よろしくお願いしますよ」
事務的な声で──実際、相手にしてみれば、ただの事務作業にすぎないのだ
──念を押し、相手は電話を切った。
──念を押し、相手は電話を切った。
「……」
「晃? お母さん、事故ったん? 大丈夫なの?」
「武庫大橋、知ってるか、夏海」
「武庫大橋? もちろん。何、あんなところで事故っちゃったの? 生協と全然違
う方向やん」
う方向やん」
「そうやんな。生協とは違う方向やんな」
「なあ、お母さん大丈夫なん? はよ、行こうよ」
「……」
晃はタクシー会社に電話をかけようとして、思い直した。
テレビの横に転がっている高城宗生の派手な色の携帯を取り上げ、『R』にリダ
イヤルをした。
イヤルをした。
ワンコール、ツーコール、スリーコール、フォーコール。
「……もしもし?」
留守電機能に切り替わるだろうかと思ったとき、高城自身の不審気な声が聞こ
えた。
えた。
自分の携帯から、女のところへ電話がかかっているのだ。
勿論、家に携帯を忘れたことは、高城自身分かっているだろうから、香澄が怒っ
て電話をかけてきたとでも思ったにちがいなかった。
て電話をかけてきたとでも思ったにちがいなかった。
「……今、どこにおんねん」
「何や、晃か。何やその口のききかたは。それに何ヒトの携帯使っとんねん」
「今、どこにおんのかって聞いとんや! 答えんかい! お母んが事故ったん
や! 迎えに来んかい! どこにおんねんお前!」
や! 迎えに来んかい! どこにおんねんお前!」
「え。事故・・・? おい、落ち着け晃。香澄が事故ったんか」
「事故ったから、お前にわざわざ電話かけとんやろ! 何度も言わせるな、さっ
さと来んかい!」
さと来んかい!」
「落ち着かんかい、このボケ。香澄は無事なんか。怪我はどんな具合や。まさ
か死なへんやろな」
か死なへんやろな」
「死ぬかアホ! 肋骨を骨折したんや、車がないから病院に行かれへん。お
前、こんな時くらいちゃんと面倒見たれや、それが出来へんのやったら、とっと
と別れろ。今やって梨花ってオンナのとこにおるんやろ」
前、こんな時くらいちゃんと面倒見たれや、それが出来へんのやったら、とっと
と別れろ。今やって梨花ってオンナのとこにおるんやろ」
「……分かった、行くわ。待ってろ」
ふいに電話が切れた。夏海は晃に取りすがった。
「ねぇ、何て? どうなったん?」
「着替えろよ。あのボケが車で迎えに来るから。入院の手続きをしに、K病院に
行かなあかんねん」
行かなあかんねん」
「そうなんや……」
晃は顎をゆがめて、掌の中の銀紫の携帯を見た。
そして、衝動的に窓を開け、思いきり道をめがけて投げつけた。
携帯の液晶画面が割れる音が二階まで響いた。
二十分もしないうちに、ドタドタと品のない足音が聞こえ、高城宗生が入ってき
た。
た。
「待たせたな。行こうか」
驚いたことに、車の助手席に、若い女が乗っていた。
『梨花』にちがいなかった。
梨花は二十歳くらいの、厚底ブーツにフェイクファーのコートに金髪、アタマの悪
そうなケバケバしい今どきの女だった。
そうなケバケバしい今どきの女だった。
夏海がささやいてきた。
「誰? あの『R』って人かしら?」
「梨花って奴や。着歴で見たから間違いないと思う」
梨花は晃と夏海が乗ってもツンとした表情を浮かべるだけで、会釈もしなかっ
た。
た。
晃と夏海も口をきく気などあろうはずもなく、ムッと漂う香水の匂いに鼻を鳴ら
し、後部座席に乗り込んだ。
し、後部座席に乗り込んだ。
「K病院やな」
「ああ」
後部座席に、カスミソウの花束があった。
「……」
晃は厭な顔をして高城の様子を見た。
高城は運転に集中していた。
バックミラーに映る高城の顔には何の表情も見出すことは出来なかった。
カスミソウは香澄の好きな花だった。
単純明快をモットーに生きる香澄らしく、自分の名にちなんだ花なので好きなの
だ、ということしか晃は聞いていなかった。
だ、ということしか晃は聞いていなかった。
が、昔から、何の行事につけても、母にはカスミソウを贈るように晃は教育され
ていた。母の日でさえ、カーネーションではなくカスミソウを贈るように頼まれた
ものだ。
ていた。母の日でさえ、カーネーションではなくカスミソウを贈るように頼まれた
ものだ。
もちろん、高城はそれを知っていた。高城も何かにつけて、香澄にカスミソウを
贈ることを習慣づけてきたものだ。
贈ることを習慣づけてきたものだ。
故に、このカスミソウは、香澄を見舞うために購入したものに違いなかった。
梨花を助手席に乗せ、後部座席にカスミソウ。
どういう神経を持てばこういう行動が取れるのだろう。
高城宗生とは、何という男なのだろう。
いや、前から真人間でないことは分かっていたのだ。
ばつの悪い沈黙が流れる車内で、車窓に流れる景色を眺めるともなく眺め、晃
は高城との五年間を想うともなく想った。
は高城との五年間を想うともなく想った。
高城宗生は、ふいに香澄と晃の部屋に転がり込んできた。
男に対しては警戒心というものを捨ててしまっている香澄が、ある日自分たちの
ボロボロの文化アパートに高城を連れ込んだ。
ボロボロの文化アパートに高城を連れ込んだ。
高城はそれきり、自分の家に帰らなかった。自分の家というものがあったのか
どうかも晃は知らない。
どうかも晃は知らない。
ただ、覚えているのは、二人のアノ時のあえぎ声。──晃の前ではしないで、と
香澄は懇願したが、高城は気が向けば遠慮なく香澄にしなだれかかり、コトを
はじめる。そんな時遠慮して出て行くのは晃の方だった。
香澄は懇願したが、高城は気が向けば遠慮なく香澄にしなだれかかり、コトを
はじめる。そんな時遠慮して出て行くのは晃の方だった。
調子のいい言葉。脅迫。暴力。うってかわったような愛想。
時々帰って来なくなる秘密めいた態度。
金が入る日は必ず香澄からせびり取り、定職に就くことは決してなく、パチンコ
と競馬と宝くじとプロレスが何よりも好きで、…要は、高城という男はどうしようも
ないやくざだったのだ。
と競馬と宝くじとプロレスが何よりも好きで、…要は、高城という男はどうしようも
ないやくざだったのだ。
やくざとは何か、晃は高城から学んだ。
やくざであるということが、いかに虚しい生き方であることか。
卑しいということが何か、晃は香澄から学んだ。
卑しいということは、何もかもあきらめて、あきらめた自分自身に嘘をつき続け
て生きていくことだった。
て生きていくことだった。
常に上っ調子の香澄。決して弱音は吐かない明るい香澄、それでいて気に入ら
ないことがあれば平気で一晩姿を消す、薄情な香澄。晃以外の肉親のもとへは
決して帰らない香澄。
ないことがあれば平気で一晩姿を消す、薄情な香澄。晃以外の肉親のもとへは
決して帰らない香澄。
そして、希望などなかった晃に希望を教えてくれたのが、アルバイト先のファー
ストフード店で知り合った夏海だった。
ストフード店で知り合った夏海だった。
夏海と知り合って愛し合ったから、晃は真人間になろうと決心したのだ、真人間
のモデルは身近にいなかったから、それがどういうものか分からなかったけれ
ども、夏海と共に生きていくなら何とかなるような気がした。
のモデルは身近にいなかったから、それがどういうものか分からなかったけれ
ども、夏海と共に生きていくなら何とかなるような気がした。
婚姻届は全身全霊をかけた晃のけじめだった。
もう年金は受けない。
もう香澄と同じ名前は名乗らない。
もう自立して生きていく、もう香澄と高城の二人とは精神的に縁を切る。
まだ家を出ることは出来ないけれど、高校を卒業したらすぐに就職先を見つけ
て──まだ就職先は見つかっていなかったけれども絶対に何とかみつけて─
─晃は今までと違う生き方をするつもりだったのだ。
て──まだ就職先は見つかっていなかったけれども絶対に何とかみつけて─
─晃は今までと違う生き方をするつもりだったのだ。
ふいにブレーキがかかり、自らの想いの中にのめりこんでいた晃の身体に重力
がかかった。
がかかった。
K病院に到着したのだった。
「花束、取ってくれ」
高城に声をかけられて、夏海がカスミソウの花束を高城に渡した。
見れば夏海は、大きな紙袋を下げていた。
「何を持ってきたんや?」
足早に駐車場から院内に歩きながら、晃は夏海に小声で尋ねた。
「とりあえずのお母さんの着替えとか。それとチョコレートケーキ、せっかく焼い
たから。……食べられる状態だといいんだけど」
たから。……食べられる状態だといいんだけど」
「チョコレートケーキ? 何でそんなもん」
「だって、バレンタインやし、今日」
「お前、そんな脳天気な」
それじゃ香澄と同じノリじゃないか。
しかし晃は思い直して黙り込んだ。夏海は着替えも準備してくれたのだ。自分
がおろおろしている間に。
がおろおろしている間に。
そしてケーキを焼いたのも、結局は夏海だった。焼きたいと言ったのは香澄な
のに。みんなで食べるのだと言って。
のに。みんなで食べるのだと言って。
──みんなで食べる? 晃はヒステリックに笑い出しそうになった。
みんなって誰だ。後ろから、梨花がついてきている。病院の陰気な廊下に、コツ
コツという四人の足音と、荒い息の音が響き渡っている。
コツという四人の足音と、荒い息の音が響き渡っている。
梨花も一緒に食べるのか? みんな仲良くご一緒に。現実逃避もそこまで行け
ば、ひとつの立派な境地だ。
ば、ひとつの立派な境地だ。
K病院は古い大きな私立の総合病院だった。
案内された病室には、サインペンで名札がかけられていた。四人部屋だった…
…斎藤智美、佐竹治弥、中嶋陽彦、そして萩原香澄の名があった。
…斎藤智美、佐竹治弥、中嶋陽彦、そして萩原香澄の名があった。
「あっらぁー! みんなで。ごめんねぇ」
香澄は、想像以上に元気そうに見えた。
「ちょっとねー、ドライブしようと思って回り道してたらドカンとやっちゃってんよ。
携帯電話は壊れるし、痛いしで連絡出来なくって、心配かけたっしょ? ごめん
ねー。でも大丈夫、もう痛み止めももらったし」
携帯電話は壊れるし、痛いしで連絡出来なくって、心配かけたっしょ? ごめん
ねー。でも大丈夫、もう痛み止めももらったし」
持ち前の甲高い声が病室に響き渡った。
同室に入院する羽目になった周囲の患者が気の毒になるような、かしましい、
いつも通りの香澄の声だった。
いつも通りの香澄の声だった。
「何やねん、もぉ。……驚かせやがって」
晃はヘナヘナと崩れ落ちそうになった。一睡もせず待っていたのに。
「ホンマやで!」
仏頂面で高城はカスミソウの花束を差し出した。
「ほら」
「あ、カスミソウやん。ありがとー。うわ、感激ぃー」
「あたしもお見舞いあるんですよ。ケーキ持ってきました」
夏海が紙袋をベッドサイドのテーブルに置き、中から紙の箱を取り出した。
「あ! ケーキだ。そうやね、今日はバレンタインやったわね。とんだことになっ
ちゃって、忘れとったわ。焼いてくれたのね、夏海ちゃん、ありがとぅー」
ちゃって、忘れとったわ。焼いてくれたのね、夏海ちゃん、ありがとぅー」
「そうですね。バレンタインですもの、みんなで食べましょう。ケーキ・・・紙皿とフ
ォークも持ってきましたから、みんなで。梨花さん、あなたも食べてください。あ
たしたち、あなたのチョコレートいただきましたから。あなたのチョコレート、食べ
たんです、あたしたちは。だから、あなたも、あたしたちのケーキ、食べてくださ
い」
ォークも持ってきましたから、みんなで。梨花さん、あなたも食べてください。あ
たしたち、あなたのチョコレートいただきましたから。あなたのチョコレート、食べ
たんです、あたしたちは。だから、あなたも、あたしたちのケーキ、食べてくださ
い」
「……」
梨花は険悪な表情を浮かべて夏海を睨みつけた。
夏海も負けずに、陰険な色をくりくりとした黒い瞳に漂わせていた。
彼女には似合わない、珍しい表情だった。
こんな顔をすることもあるのか、と晃は内心驚きながら夏海を見た。
「梨花さん、……ひさしぶり」
梨花に声をかけたのは、晃たちが驚いたことに、香澄だった。
「……死んでしまえばよかったのに。あんたなんて」
「こら、梨花!」
高城が梨花をたしなめた。
赤茶色のマスカラに縁取られた梨花の瞳から、ぼろぼろと涙がこぼれ落ちた。
「あんたが死んでしまえばお父さんが帰ってくるのよ! あたしたちの家に!」
「梨花!」
晃は肝をつぶした。
──お父さん?
「場所を考えて騒げ。それに、香澄は悪くない、悪いんはおれや」
「そうよ、お父さんが悪いのよ! だけどみんな悪いのよ! うちがどうなったか
あんた達知ってるの? 知らないでしょう!」
あんた達知ってるの? 知らないでしょう!」
晃は面食らった。何も知らない。
「あの……、」
夏海がおそるおそる口を開いた。
「梨花さんは高城さんの娘さんなんですか? そのぅ、いわゆる『パパ』とかいう
んじゃなくって、その、何と言うか、血のつながりのある……」
んじゃなくって、その、何と言うか、血のつながりのある……」
「馬鹿にしないでよ! もうイヤあっ!」
梨花はいきなり走り出そうとしたが、高城に腕をつかまれてつんのめった。
「梨花、お父さんが悪いんや、それは分かってる、けど待ってくれ。晃たちは悪く
ないんや。お前もここで少し話して行ってくれ」
ないんや。お前もここで少し話して行ってくれ」
「何てワガママなのっ、いつもいつも!」
喚きながら、梨花は暴れた。
「ごめんなさい、梨花さん…」
香澄が手を伸ばそうとして、
「ア痛ッ」
と手を引っ込めた。晃は慌てて香澄を支えた。
「どういうことやねん、お母ん。このヒトが高城サンの娘さんってことは、この梨
花さんのお母さんがいるってことか? じゃ、高城サンとお母んは不倫……」
花さんのお母さんがいるってことか? じゃ、高城サンとお母んは不倫……」
「晃! 声が大きいって」
夏海が晃の袖を引っ張り、晃は周囲に人がいることを思い出して口をつぐんだ。
しかし時は既に遅く、同室の全員の視線がこちらに集中していた。
しかし時は既に遅く、同室の全員の視線がこちらに集中していた。
「す、すみません、取り込みまして。静かにさせますんで、皆様、ごめんください
ー!」
ー!」
香澄が素っ頓狂な声で叫んだ。
目も当てられない。
晃は声を抑えながら続けた。
「……つまり、高城サンには奥さんがいるってこと?」
「いや、もうとっくに離婚しとるで」
「でも不倫してたってこと?」
「まあ、そうなるな」
晃は空いた口がふさがらなかった。
高城の携帯の『R』は娘だったのだ。
高城は娘とデートをするのを楽しみにしていたのだ。
そして、香澄は全部承知だったのだ。
高城が梨花のもとへ通うのを黙認していた。
それはそうだろう。最初に香澄が、梨花の母親と梨花から、夫であり父であった
高城を奪い取ったのだから。
高城を奪い取ったのだから。
ロクでもない男とはいえ、梨花たちにとってはかけがえのない存在だったのに
違いない。今でも会っているくらい仲の良い父娘なのだ。
違いない。今でも会っているくらい仲の良い父娘なのだ。
何と言えばよいのだろう。
晃は言葉が見つからなかった。
自分は被害者だとばかり思っていた。
が、被害者は梨花だったのだ。
梨花にしてみれば、自分は、憎んでも憎みきれない加害者の息子なのだ。
知らなかった……。
晃はどうしても梨花にかける言葉が見つからなかった。
何を言えるというのだろう、この状況で。
高城がうめくように言った。
「ごめんな、梨花。でも、おれはお前のことも愛してるし、香澄のことも愛してる
んや」
んや」
「お母さんのことは愛してないのね」
「……ごめんな。おれが悪いねん」
「許せない」
「あの」
口をはさんだのは、夏海だった。
夏海は皆がもめているあいだに、いつの間にか、チョコレートケーキを切り、紙
皿に取り分けていた。
皿に取り分けていた。
「梨花さん、ごめんなさい、事情が分からなくて……、あたし。でも、あの、…良
かったらケーキ食べていただけませんか。上手く焼けたつもりなんです。あたし
たち、あなたに頂いたチョコレート、勝手ながら美味しく食べてしまったんです。
ごめんなさい、無神経で。だけど、今日はバレンタインだから、チョコレートケー
キを食べませんか? あたし、ご一緒に、食べたいんです、あなたと。お互いの
存在を無視するんじゃなくて、一緒に、何かの形で、…上手く言えないけれど、
一緒にバレンタインを祝えるような仲になれたらいいなぁって、高城さんが愛し
てる娘さんの、あなたと。みんなで食べれたらいいなぁって……」
かったらケーキ食べていただけませんか。上手く焼けたつもりなんです。あたし
たち、あなたに頂いたチョコレート、勝手ながら美味しく食べてしまったんです。
ごめんなさい、無神経で。だけど、今日はバレンタインだから、チョコレートケー
キを食べませんか? あたし、ご一緒に、食べたいんです、あなたと。お互いの
存在を無視するんじゃなくて、一緒に、何かの形で、…上手く言えないけれど、
一緒にバレンタインを祝えるような仲になれたらいいなぁって、高城さんが愛し
てる娘さんの、あなたと。みんなで食べれたらいいなぁって……」
「……」
梨花が鼻をすすり上げる音がシンとなった部屋に響いた。
梨花の視線と夏海の視線がからみ合った。
夏海はふっと視線をそらし、持参した紙袋の中から白いタオルを取り出した。そ
してタオルとケーキを梨花に差し出した。
してタオルとケーキを梨花に差し出した。
「……」
梨花は唇をかみ締め、タオルを受け取り顔を拭いた。
そしてケーキを受け取った。
「フォークも、どうぞ」
「……」
梨花はおとなしく受け取った。
夏海は晃と香澄と高城にも、それぞれチョコレートケーキとフォークを手渡した。
高城が紙コップに枕もとの急須からお茶を注ぎ、それぞれに手渡した。
高城が紙コップに枕もとの急須からお茶を注ぎ、それぞれに手渡した。
「……あたしたち母娘だって、一緒にバレンタインをお祝いしたかったんですよ。
お父さんと」
お父さんと」
梨花がポツンと言った。
「今一緒にいるのが、あなた達じゃなくて、あたしのお母さんだったらいいなぁっ
て思う。分かるでしょう?」
て思う。分かるでしょう?」
「……分かります」
「だけど、今一緒にいるのはこのメンバーや、ってこった」
高城が、いけしゃあしゃあと言った。
「バレンタインに乾杯すっか。それと香澄の無事を祝って」
「馬鹿」
はからずも、梨花と香澄の声がハモった。
香澄は彼女にしては珍しく、遠慮して口を閉ざした。
「ホンマどうしようもない馬鹿やね、お父さんって。……でも、たしかにそうやわ。
今ここにいるんは、あたしのお母さんじゃなくってあなた達。悲しいことだけれ
ど、どうしようもないことってあるよね」
今ここにいるんは、あたしのお母さんじゃなくってあなた達。悲しいことだけれ
ど、どうしようもないことってあるよね」
「どうしようもないよな……」
晃は申し訳なく感じながらも、思わず口走ってしまった。
五人はケーキを頬ばった。
「少し苦すぎやわ、このケーキ」
梨花がもそもそとつぶやいた。
「今日を記念日にしませんか」
晃はふと、こみ上げる想いに突き動かされて、梨花に語りかけた。
「は?」
「おれと夏海は、昨日結婚したんです。役所に籍を入れに行ったんです。せや
から、昨日が結婚記念日やと思ってました。指輪も、こんな三千円ぽっちの指
輪やけど買って、夫婦気取りでおって、……でも、…今日にせえへんか、夏
海? 結婚記念日を。おれ、皆の前でもう一度誓いたいねん。みんな、聞いてく
ださい。おれは、夏海を一生愛します。浮気はしません。おれは全力で夏海を
幸せにします。そして、梨花さん、梨花さんも、一生ひとりの人を愛するって誓
いませんか」
から、昨日が結婚記念日やと思ってました。指輪も、こんな三千円ぽっちの指
輪やけど買って、夫婦気取りでおって、……でも、…今日にせえへんか、夏
海? 結婚記念日を。おれ、皆の前でもう一度誓いたいねん。みんな、聞いてく
ださい。おれは、夏海を一生愛します。浮気はしません。おれは全力で夏海を
幸せにします。そして、梨花さん、梨花さんも、一生ひとりの人を愛するって誓
いませんか」
「……そうね。お父さんにはイヤミに聞こえるかもしれへんけど、ホンマそうやと
思うよ。あたしも一生、ひとりの人を愛したい。だけどね、何も保障はないでしょ
う。だから、あたしが誓いたいと思うのは」
思うよ。あたしも一生、ひとりの人を愛したい。だけどね、何も保障はないでしょ
う。だから、あたしが誓いたいと思うのは」
梨花は皆の顔を見回した。
「あたしは晃さんたちの誓いを見届けた。それは誓える。それと、一生、現実を
受け入れるということ。それを誓おうと思う。今までやって、ずっとそうしてきた。
あたしは、お父さんがお母さんを裏切っても、お父さんを愛し続けた。あるがま
まのお父さんを受け入れようと思ってきたよ。これからも、そんなふうでいたい
の。あるがままに、ありふれたこんなつまんない自分と自分の周りを愛そうと」
受け入れるということ。それを誓おうと思う。今までやって、ずっとそうしてきた。
あたしは、お父さんがお母さんを裏切っても、お父さんを愛し続けた。あるがま
まのお父さんを受け入れようと思ってきたよ。これからも、そんなふうでいたい
の。あるがままに、ありふれたこんなつまんない自分と自分の周りを愛そうと」
「それって素敵」
夏海が泣き笑いの顔で微笑んだ。
「あたしも見習うわ。あるがままに、ありふれたつまんない自分と、自分の周りを
ね。あたしもそんなものを一生愛するわ。ね、晃」
ね。あたしもそんなものを一生愛するわ。ね、晃」
「アンタたちにはアタシが悪者に見えるかもしれないけれど」
香澄がケーキを咀嚼しながらつぶやいた。
「アタシもずっとそんな願いを持って生きてきたんよ。あるがままにさ。ありふれ
た自分や自分の周りを愛していこうって。だけど、うまくいかなかったのかなぁ。
親や兄弟が許せなかった」
た自分や自分の周りを愛していこうって。だけど、うまくいかなかったのかなぁ。
親や兄弟が許せなかった」
「おれは許したるで」
晃は言った。思わぬ言葉が口をついて出た。
「許せへんけど、許すしかないやん」
「そうやね」
梨花がつぶやいた。
「何が起こるか分からへんけど、憎むよりも、愛しながら生きたい……」
夏海は黙って、そっと晃の右手を握り締めた。
夏海の左手の指輪の硬質な感触が、晃の右手の指先の神経を通り、脊髄を通
り、彼の脳を何とも言えない緊張感に震撼させた。
り、彼の脳を何とも言えない緊張感に震撼させた。
<おわり>
(2002・2・11)


☆この物語はフィクションです。実在の人物・団体とは関係ありません。


